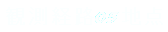ss
No other life
「海に行かない?」
同じ部屋にいて別々のことをしていた来訪者が、突然そう告げたのは、決して晴れ渡るような日なんかじゃなくて、むしろ雲が空をびっしり覆うような、昼間でもどことなく薄暗い、そんな冬のある日のことだった。
「………さむいっ」
この年頃にしては、若干低めの――彼女は落ち着いていると言ってくれる――普段あまり抑揚しない自分の声が、この時は少し高めに、そして跳ねるように辺りに響いた。
「ね。多少ぶさいくでも、やっぱりダウンコート着てきてよかったでしょ?」
――そういう問題じゃない!
私よりもずっと高い、少女らしい弾んだ声がそう答える。
少し(いやかなり_)論点のずれている相手と私は、少しの距離をあけて、今まさに寄せ
ては返す海岸線の真っ只中にいた。
少しではなく半端なく風が強い。
それらのもたらす感覚は、ただ「刺さる」。
けれど、辺りには全く人の姿がなかった。
それも当然。今日は平日。時間にして午後三時。
近頃は日も伸びてきたから、五時を過ぎてもまだ空に夕日が残っているぐらいにはなってきた。
「っ…!」
突然ものすごい轟音が空を抜けていった。
冬は若干の耐寒性をもたらす、自分の長い髪が前方へとなすすべなく流れていく。
見上げると、一機、旅客機が空を横断したところだった。その影は普段都心で見かける程の豆粒ではなく、
なかなか見れないぐらいの重量感を感じさせる飛行機の全景だった。
(まるで魚のお腹みたい)
すでに滑車を畳みこんだ滑らかな機体を見て、そう感じる。
「…………」
何か叫ぶかと思ったら、以外にも目の前の少女は荒れる海面を眺めているだけだった。
「……」
何度目かの飛行機が飛んでいく。私ももう近づく轟音に、いちいち反応しなくなっていた。
気温10度。私の中では、10度が基準として冬の温度は判断されている。
10度を切れば予断を許さない。10度あれば、そんなにひどくはない。
耐えられない、寒さじゃない。
・
・
・
セミダブルベッドに二つの影が並ぶ。
薄暗い部屋。目が慣れてくれば、窓からの街灯も手伝って、そんなに窮屈でもなかった。
「…………」
「………」
会話はない。けれど寝ているわけでもなかった。
ただ寝息よりも静かな呼吸音だけが、二人の耳に届いていた。
私はうつ伏せに、彼女は右肩を下にして。ベッドの中央に向かって顔を寄せ、視線は交差する。
その間で、一つ静かに、二人の唯一の部分が繋がりを示していた。
「…………ねぇ」
「うん…?」
会話は、続かない。
寝ないの?ともそれ以上のことも、余計な差し障りない会話は一切なかった。
別に、気まずいとも思わない。
その時私が感じていたこと、彼女と共有できていたかはわからない。
私達二人、同じ水槽の中にたゆむ、二人っきりの熱帯魚だったらいい。
水も空気も光も、全て同じものを共有できていたらいいのに。
(――あなたは私の想い人)
唐突にそんな言葉が、胸をついた。
お互いの呼吸は、いつしか同じリズムを刻んでる…風に感じる。
なんの奇跡か気まぐれか、二人同じ想いを通わせられた偶然に、私達は身動きが取れなくなる。
手をぎゅっと、握りなおしてみる。けれど、その温かさが、何らかの意識の抵抗――背けられない禁忌を――私に迫った。
温かい。…心地いい。
触れられて、幸せ。触れたい。
感じたい。けれど、
きっとこれ以上は……『冗談では済まされない』
ごめん、こんな……つまらないことに付き合わせて。
ううん、いいの…。というか、それを言うなら私の方が…。
うん、そうだね……。
私達は二人、両思いという名の網に掛ってしまった。
抜けだせない。けれど息が詰まる。
逃げ出したい。けれどもう手放せない。
距離を詰めて、身を寄せ合えば、余計にその想いは強くなるだろう。
――今ならまだ引き返せる。
この橋を渡れば……『もう戻れない』
離れ過ぎるには息苦しく、近づき過ぎれば切なさに身が焦がれそうで。
私達二人は、近付き合えない。
なんて…XXXだろうね。
何に躊躇ってる。何に遠慮してる?
何に迎合してる。何に媚びている?
そんなのわからない……
…
同性同士の秘密の付き合い。
世間にも社会にも背いて。
本当、なにやってるんだろう。
――覚悟が、できてない……
「私、涼子の可能性を奪ってるだけなんじゃないかなって、たまにそう思うの……」
……
…
あんまりにも偶然の産物だった。ここにひとつのカップルが出来あがったのは。
友達の友達という、ありきたりな出会い方、そして最初の一か月は確実に、二人きりになれば
あのとびきりな気まずさを味わう、そんな関係性で、私達は出会った。
特に趣味があったわけでもなく、会話のリズムがいいわけでもなく、相性もいいわけではなかった。
けれど自分が…無理せずいられる人。
今時の女子ほど、テンションが高くない私は、よく相手に気を遣わせるらしい。
自分のいないところで、偶然耳にするのはよくある陰口。
「西藤さんといると、こっちばかり気使って疲れちゃう」
ほんの少しの、心に刺さる棘と傷。
次の日には忘れてしまうぐらいに些細なものでも、日常のなんともないきっかけで脳裏によみがえってくるものであり。
無意識に働くそれが、私から私を奪っていく…。
またこの子も…私のことを負担と感じるのだろうか。
わかってるなら、治せばいいのに。
矯正すればいい。強制すればいい。
けれど、
……
…
「高城さんと知り合い?」
「え? …うん、一か月前ぐらいから。一緒に遊ぶ機会があって…」
「あの人ってさ、少し変わってない? 人の話聞いてるのか聞いてないのか。いつも我関せずって感じで、人に興味持ってなさそうっていうか…」
…、…。
この人は、あの時私の陰口を言ってた人とは、違う人。
どんどんと、会話尻が耳に入ってこなくなる。
「…特にそう感じた事はないけれど」
相手は少しだけきょとんとした顔をする。
そしてしばらくしない内に、私から去っていった。
でも本当のことだった。私は彼女が変わりものだと感じた事は一度だってない。
あるとすれば……確かに、彼女はマイペースだなって、微かに感じたことぐらいだった。
「こんにちはっ、西藤さん」
「!」
後ろに振り向くと、彼女がいた。
「一緒に飲み物でも飲みませんか?」
「……」
僅かに、上昇する心拍数。
今の話、聞かれたのかしら…。
手渡されたのは温かいミルクティ。おごってくれたけど、好みを聞いてくることもなかった。
「…………」
「………」
自販機近くのベンチに腰掛けて数分。
会話がない。
困った、ね。
「実は、来週一緒に遊びに行くことになってたじゃないですか? 3人で」
「あ、…そうですね」
「…あれ、智子がダメになっちゃったみたいで。良ければ二人で行ってきてって話になったんですけど」
「……そうなんですか」
「どうします?」
「………」
あとで聞いたら。
佳織は色々と裏で工作していたらしい。
智子に言い訳して、辻褄合わせて。佳織自身から白状されるまで明らかにならなかったのは、私がいちいち日々のことを智子に報告したり、連絡する性格でなかったことが最大の功労らしい。
そんなこと言われても、あぁそうなんだって感じだよね。
一緒にいることが多くなって、
それが彼女がしてることだなんて気づきもしなくて。
いつしか、名前で呼び合うようになって。
気まずさなんて、いつ頃なくなったか気付きもしないぐらい月日が経った頃。
私達は、高一になった。
うちは女子校だけれど、どういうわけか、高校に上がってから自ずと異性に関する話が多くなった。
バイト先の先輩が、後輩が。
合コンをいつ開くか、どんなメンツか。
どこまでいったとか、そんなこと。
大人達の作った常識や世間が私達を取り込む。
大きな流れが、私達を巻き込んでいく。
私達はどれだけ、自分がそれに当てはまったかと、嬉々として自慢しあう。
私、流行から外れてないよね、と…。
「涼子、高校に入っても羽目を外し過ぎないようにね。…幼稚園の頃一緒だった、坂木さんって覚えて
る?
今日、坂木さんの母さんに偶然会ったんだけど、…やっぱり高校に入ると色々とみんな背伸びす
るみたいね…。
せめてもう少し待ってあげて。今だと、お父さん卒倒しちゃうだろうから」
あながち、嘘でもない……――
「誘われた。戸松さん達に。」
「なにに?」
「合コン」
「そう。行くの?」
「行かない。興味ないから」
「そう」
偶然だね、実は私もついさっき、彼女たちとは別の人に、合コン、誘われた。
けど言わない。いちいち自分のことを報告したりはしない。
「彼氏作ったりしないの?」
「…友達なら、別にいるし」
「特定の誰かとか」
「………どうしてそんなこと聞くの」
「……」
速い流れは私達を捉え損ね、その代わりに私達は大多数の安全圏外へと弾き飛ばされる。
少しいじわるな質問をしてみたかった。
こんなこと普段ではいちいち聞かない。
わずかに苛ただし気な態度になる佳織。見るからに嫌悪を顔に示す、こんな表情を見るのはゆえに初めてのことだった。
「みんながおかしいの」
「確かに」
智子は智子で、お決まりのバイトデビュー。
そんなに理想通りに行くものでもないらしく、なかなかに苦戦中みたいだった。
「みんな流されすぎだよね。世間一般論に」
「流されてみたら。きっと楽だよ、今よりも」
「それって経験論?」
「ううん、本の受け売り」
「…………。涼子さぁ、近頃よくそういうこと、勧めてくるよね」
「そうかな?」
「そうだよ」
広い空間は薄暗く。ぽつんぽつんと所々にライトアップされるのは、小型の水槽。
ここは東京の某有名ビル。そして今の期間は、アクアリウムの展示がされている。平日の午後3時。人は少ないけれどさすが東京。
どこからともなく、カップルが雰囲気に酔いに来てる。
「どうしてそういうこと、言うの」
「…………なんでかな」
「ふざけてる」
「ふざけてないよ」
「……なら。そういうこと、あまり言わないで」
「…………」
素直じゃない。”わかった”って、そう答えれば穏便に済むのに。
「はい、は?」
「…あなた、私のお母さん?」
「違うけど?」
「私、子供じゃないよ」
「でも聞きわけが悪いね。…珍しい」
ぷいっとしらんぷり。
目線の先にはまばゆい水槽の中で、エビが一生懸命草原のような水草の上で、こけ取りに勤しんでいた。
眩い人工照明に照らされるそこは、まるで楽園のよう。
「涼子こそ、どうなのよ」
「ん?」
「ボーイフレンド、作る気ないの?」
帰り道。頭の中はすっかり空っぽ。
ビルの外の、変わったオブジェが飾られる遊歩道を、珍奇だなぁなんて感じながら、ぼんやりと眺めていた。
「興味ない」
「ならバイトとかは」
「今は勉強で忙しいの」
「……そうは見えないけど」
「学生の本分は勉学でしょう」
「使い古された格言」
「それにさ、真面目に答えるなら。好きな人ができたなら別だけど、作るのとは少し違うんじゃないかなって
思う。ついでに女子校。作ることに意欲がないなら、出会いなんてそうそうあるものじゃない」
「…………。出会いなんてそこかしらにあるじゃない。例えば電車。毎朝同じホームから乗り込めば、いつし
か顔見知りの学生ができるかもしれない」
「……ふふ、あの満員電車の中では無理でしょう」
「それじゃあ学校の先生だっていい、月一で体育館借りに来る、他校の生徒達だっていい」
「………どうしたのよ、佳織…」
「……なんだっていいのっ。目線は追いかけるでしょう、自然と無意識に。そうしていつか。涼子の言う、
”好きな人”っていうのはできるものなのよ…。情けないほど……、たわいもない出会いから」
「そうかなぁ」
「そうだよ。涼子は子供だよ」
「…今日はやけにつっかかる」
「だって全然わかってないんだもん」
……
…
仕組まれた罠だった。
成長の遅い私に対しての、皮肉な一手。
「佳織に好きな人ができたぁ?」
「うん、そうらしいよ…」
「だれだれ」
「隣の区の……」
その時初めて芽生えた感情は、焦り。切迫感。
どちらかというと、感覚が愚鈍な自分が、生まれて初めて感じた、強烈な感情だった。
だから、よりにもよってなぜ”焦り”なのかって、戸惑いも感じた覚えがある。
焦りとか理不尽さとか。そこからの怒りとか、憤り。
寂しさ。大切な何かを手放したかのような空虚感が、胸の片隅に小さくぽっかり。
…!
「キスしたいって、想う人だよ」
顔が近づいて、
「…っ、」
「もしくは、キスされても、嫌じゃない人」
そして離れた――
たった1,2秒を、こんなに長く感じたのは初めて。
切り抜いてしまえば、さっきまでの真剣な表情の佳織と、0目の前の、顔を紅くして気まずげにそっぽを向く佳織。
その二つが連続する程度にしか覚えてない…。
「だ~ま~し~た~な~~」
「だってこうでもしなきゃ、成長の遅い涼子は、恋が何だか気づかないじゃない」
ついでに言うなら、希求と寂寥。……。
「そして私は……涼子も巻き込んで。どんどんと罪を被っていく」
「……?」
佳織が発した最後の言葉の意味が、その時の私には理解することができなかった。
「ねぇ……! なんで……な、ん、で、こんなところ、来たのーーー?」
風の音、さざなみの音、飛行機の音。
何もかもが耳をついて、二人の音の距離を阻んで、私はさっき以上に甲高い声を上げた。
「…………。さぁね。よく、わかんなぁーーーーいっ」
「むぅ…」
その『よくわかんない_』に、付き合わされるこちらの身にもなって欲しい。
「涼子、つい最近風邪引いたばかりでしょ、引くことはないよーーーー」
「意味がわからないーーーーー!!!」
まるで奥深い山の頂上に来てしまったように、私達はできうる限りの大きい声を張り上げて、僅か数mにいる相手に話しかけていた。
「ちょーーーーーーーさむいね!」
「ヴぁか!!!」
振り向いて満面の笑顔の相手に、無性に腹立ちながら…でもどこか愉快な気持ちで、とびっきりの罵声をプレゼントした。
「あっははっ」
風と寒さと潮風のせい_?佳織の瞳にはどことなく涙が溜まってる。
それは私も同じかもしれない。
「風邪引いたら、佳織のせいだよ!」
「え?なにー?聞こえなーーーーい」
「それ聞こえてんでしょ!風邪、引いたら!佳織のせいだからねーーーーー!!」
「わかったぁーーーー」
足もとには流されてきたか、もしくは公園によって配置された、かなりの大きさの大木。樹皮ははがされ、つるつるになってしまっている。
そこにさっきまで私が飲んでいた温かいお茶が、飲みかけの状態で危うげに放置されていた。
「…………私達、どこに行っちゃうんだろうね」
「……。」
「世間からも親からも……見離されて」
「……佳織…」
寒さを感じなくなった頃、ぽつりと佳織が呟いた。
風に流されず、それはその場に居座りように、ぼんやりと残る。
「貝綺麗。結構流れ着くものなんだね」
「…」
「涼子はいつまで私と一緒にいてくれる?」
私が顔を向けたのと、佳織が腰をかがめたのは同時だった。その間、数秒。
咄嗟に目に飛び込んだのは、そのむき出しのふくらはぎ。
一秒もしない内に認識したのは、靴を脱ぎ捨てた真っ白な足先と、両手でまくりあげられたスカートだった。
「佳織!?」
佳織の突然の行動に、動揺していたのは事実だった。
けれどそれとはまた別の理由で、私の内心は発作でも起こしたぐらいに、バクバクと
高鳴っていた。砂浜に映える脚は細く、白く。…厭に艶めかしかった。
海を荒らす強い風。絶え間ない波間。ちょうどまた、頭上を横切った飛行機の轟音。
いろんな音が、私の耳を満たす…中で、佳織が私の横を駆け抜けていったのは、一瞬だった。
「…佳織!」
彼女の後姿が、真っ白い波しぶきの中に、消えていく。
咄嗟に背中を追う自分の足もとが、もののうちに冷たく重くなっていく。不快な感触が絡みついていく。
冬の海は、とてつもなく体を突きさした。
さっきまで吹きさらしになっていた体は、既に「冷たい」という感覚から「麻痺」へと変わりつつある。痛い、冷たくて、とてつもなく痛い……っ。
「……………馬鹿ッ!」
海面が胸まで達した頃、私は自分の腕の中に、何かぐったりとしたものを抱えていた。
「ばかばかばかばか…! どうしてあんたはそう、……そう…ッ」
「……えぐ……っ…」
「どうしてひとりで抱え込むのよっ、どうして何も話してくれないのよっ、どうして……
こんなになるまで……いつも、…いつも……」
「涼子はいつまで……私と一緒にいてくれるの……?」
「……ばかっ……わからないわよ、そんなの私にだってわからないっ……!」
なぜか、涙が溢れてきた。
冷たさしかないはずの状況に、とてつもなく熱い、体の内から溶け出すような、こみ上げる雫。
「あは…、どうせなら、”涼子がいつまで私と一緒にいてくれるのか”本当にわかればいいのに。そうしたら、それまで全力で、後悔も希望もないぐらい、瞬間瞬間、楽しめそうなのに……。…涼子、私ね……あなたといつまでも一緒にいられても、不安な気がするの。あなたが離れていってしまうのも、もちろん……」
「わかってる……、わかってるから…」
「…うぅ…ッ…」
涙と海水で、ぐちゃぐちゃになった佳織の頬を、両手で包む。
「…………」
以前としてしゃくりあげる佳織と、私は……そのまま何もできない。
唇を近づけることは、またひとつ罪を背負う。そんな気がして、これ以上動けないでいる。
だからぎゅっと……出来うる限りの力で、佳織の体を抱きしめた。
佳織の体も、私の体も。とっくに感情の高ぶり以上に、冬の海の冷たさに、体を震わせている。
「一緒にいる。ずっと一緒にいるから…。なにがあっても、どんなときでも、ずっと一緒に
いるから……っっ」
「うん…、うん…っ」
……
…
割れる曇り空。覗く太陽の存在。
まぶしい光が、直線に降り注いでくる。
棘が、私達の体を、ひとつにするように、四方から突き刺さってくる。
意識を霞ませながら、私達はお互いにもたれ掛かっていく……。
二つの影が、一つになる。
UP 2011/2/14
無断転載・引用禁止
Copyright(C) nokizaka All Rights Reserved