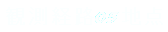girls
この物語はフィクションです。実在の人物・団体等とは一切関係ありません。また、決して作品中で行われている行為を推奨するものでもありません。絶対に真似しないでください。
閲覧した上で起こったトラブル・不快感に関しては責任を負いかねます。
どうしてこう、人は分かり合えないのでしょうか。
人間は退屈なことが嫌い。
だから様々な娯楽を造りだす。
退屈に心が蝕まれないように、つまらないに心が向かないように。
だから夢中になれるものを作り出す。
生きている限り付きまとうこの虚無と空虚を一瞬とその連続忘れさせるために。
人工物を造る。投与物を造る。
そうして弱い心をコントロールする。
人間は、とても弱いものだから。
生と生きることそのものを否定しないように。
prologue
そこは東京のある有名な繁華街。
若者が集まるその街に、埋もれてしまうほどの細い鉄筋ビル。
夜な夜なそこは、どこからともなく羽のもげた若者たちが集まってくる。
這い蹲るように、救いを求めるように。
僅かに地下に差し掛かる古びた鉄扉を押し開くと、そこは照明は僅かの薄暗い空間。
ただし、すぐそこにも人は溢れ返っており部屋全体を確認することはできない。
それでいてどことなく煙たい。喉に沁みるような、張り付くような白い煙。
目に付くのは、ホールにかかる音楽に体を揺らす若者たちだけではないということ。
至る所に壁際には気だるそうにもたれかかる姿もあれば、それ以上に力が抜けたように
座り込んでしまっている姿もあった。
その顔は照明のせいか垂れかかる前髪のせいか、はたまた本人の顔色のせいなのか影をさしていてよくわからない。
そしてまた、一つの影が扉から抜け出てくる。部屋全体に扉の隙間から長い影が伸びる。
その姿は一見普通の女子高生。街で目にするような特徴のないデザインの制服。その割には髪は目立つ手を加えていない黒色。
その分艶があり、滑らかな動きをまとっている。
顔つきはひどく整っており、間違いなく美人。やたらに細く白い足が嫌が応にも人の視線を引く。
ありふれた少女のようで、そうでない。どことなく引っかかるような違和感をぬぐい去れない、そんなアンバランスな印象を受ける少女。
……わかるものがもし至近距離で確認できたなら理解できただろう。その纏う制服は量産品ではない。まぎれもなく学校指定の制服。
高級布地によって仕立てられたものだ。履く靴も持つ鞄も本革。金額は、見た印象よりもずっと高い。
「私は、……私」
切れ込むような、不適な笑みが口元を飾る。
彼女に対して何か言うものは誰もいなかった。
***
同じ頃――
風の吹く夜の屋上。風が強く、服と髪が何もない闇夜の空間へと棚引く。
「私も、まだまだね…」
手放したい感覚、感情。世情と浮世。
なのにどこかでまだ怯えている、私の、人間としての理性、本能。
本当はもう、さっさと楽になってしまいたいのに。
手の中の小さいビニールの袋をぎゅっと握り締める。その中には白い粉。
「ダメダメね。私」
夜の帳に落ちた深い墨色の空を仰ぐ。
風が一陣、横に薙いだ。
ごめんなさい――
episode 1
うぅ、うぅ……、苦しい……。
この虚無感、たまらない。
苦しい、苦しいよ……。
這いつくばるように、私の体はある場所へ向かっていく。
頭と心と体が切り離されたかのように、私の理性はどこかへ飛び、勝手に踏み出す足は
8ミリカメラの映像のように自分とは関係ないような事実として映る。
あそこに、行かなくちゃ……。
『バンッ』
突如大きな鈍い音が耳に響く。私は咄嗟に身を竦める。
私の手が、腕が、前に投げ出され、砂嵐みたいな映像の向こうで『私』がドアを開け放っていた。それを知って理性のどこかでなんてバカなのかと囁く。
あれ、もうついたの……。
早く、早く行かなきゃ……。
不審な私にその建物にいる人間が何かと一瞬振り向くけど、それはすぐに元の興味に戻される。慣れきってしまっているのだ。
私の足は、そのまま階段を求めて進む。自分の足なのに、しっかりしない。まるで地震の最中にどこかに行こうとしてるみたいで、視界さえもぐらぐら揺れてる。
薄暗い部屋。煙たい空気。ぼやける照明。耳鳴りのようなBGM。
無骨な鉄筋コンクリート。私は、いつのまにか風の吹く夜の屋上にいた。
「はぁ、はぁ……」
体力不足の体には、ちょっときつい運動だ。
さぁ、早く……。
震える手で、手のひらサイズのビニール袋を慌てて取り出す。
普通なら何でもない動作なのに、このときばかりはまるで跳ねる魚でも捕まえているかのように袋は跳ね、上手く自分の体を動かせない。
袋の中には、白い粉。
ようやく開いた袋を、手の平に落とそうとする。少なくない量の粉が、風に飛んでいった。
あとは、あとはこれを、口元に……。
当てれば終わり。
「う、ぐぅ……」
怖い。
怖いよ……。
「っ……」
粉を掴んでいた私の右手が口元を通り過ぎ、空を横切る。
一瞬で、手のひらの中の白い粉は空へと舞った。りんぷんのように。
「ばか、……ばかっ……」
なんでいつも、どうしていつも済んでのところで思いとどまるのよ……!
僅かに残された理性が私のおろかな行為を押しとどめる。いつも。
それは何より私が理性的な人間であることの証拠。一時の感情と欲望に押し流されない、ただのへたれ。
「うぅ……」
いつも、いつも、私の胸ポケットにはこの小さいビニール袋が忍ばされてる。
それはお守りのように。それ自体が安定剤のように。
今まで、何度か使用しようとしたことはある。けれどいつも踏みとどまっていた。
勢いに任せて全てを投げ出してみたい衝動。それを押しとどめる理性と本能。
原因不明のこの虚無感。焦燥感。言い知れない不安。
怖い……、助けて、誰か、助けてよ……。
手すりの向こう、おそらく地上で、救急車が走り去っていったんだろう。
嫌に響く、空しい特徴的なサイレン――
霞んでいた視界が、徐々に鮮明に戻ってくる。私の中で意識と現在の状況が重なってくる。
「いくじなし……」
何度目かの、後悔――
やがて朝日が昇る。気づくと私は屋上のベンチにもたれかかるように眠っていた。
ふと自分を見れば、制服姿だから驚く。いつ、着たのだろうか。それとも、着換えないで
ここまで来たんだっけ? わからない、わからない……。
オレンジ色の光が、そんな私の視界をいっていた。まだ昇りきってない太陽。
今日も、日常がやってくる。
「また、学校か……」
鞄はどこだっけ? シャワーは? 朝食は?
こんな時間に開いてる店は、……店なんて、ある?
わからない、わからないけど……。
行かなくちゃ。『いつも』の中に……。
「眠い……」
一人の女子高生が、まぶしい朝日の中いつもの見慣れた通学路を歩いていた。
通学路といっても、典型的な住宅街を行くわけでもなく、商店街の中を抜けていくわけでもなく、はたまたちょっとした規模の並木道の中をいくわけでもない。
通学路と聞いて想像するようなイメージとは間逆の、彼女の年齢からしたら数年後先通うことになるであろうオフィス街を思わせる町並みをただ行くだけ。
所々に景観を意識した緑が植えられてはいるが、実際は大半をコンクリートに囲まれた街並みを、特徴のないデザインの制服が抜けていく。
そこは東京にある名だたる歴史ある学校と比べたらあまりにも歴史も伝統も浅い、新設の女子高校。
校舎さえも従来の学校からイメージする建物ではなく、まさに都心にある大学のキャンパス風である。
歴史は浅いが、その分古い体制、しきたりに縛られることなくあくまで生徒の自主性を重んじ、校風は自由。生徒の幅広い才能、個性に合わせた専門的な学習、フォローを行うことで有名であり特色だった。
逆にしっかりしていないと何をしていいのか目的も決められないまま生活を送りかねない校風のため、志願者、在校生共にどことなく
大人っぽく自律心のあるしっかりした子が集まっていた。偏差値は、新規参入校にしては、間違いなく高い。今、新しいタイプの学校として内外に注目されている。
彼女間堂操は、私立律奏(りっそう)学校の生徒だった。身を包む制服も鞄も靴も、デザインは特徴がないながらその作りは間違いなく精巧でまぎれもなく高級品。
「ふぁー」
彼女が欠伸を億面もなくすれば、徐々に作られ始めた流れの後ろの方から一つ影が飛び出し、その肩を叩く手がある。
「おはよう」
「あ、おはよう…」
「今日朝から古典だねー」
「そうだね」
あの先生はろくに生徒をささないから、睡魔との闘いだだの。それでも授業の端端でテストに出るところを指摘するため
寝てもいられない。そんなたわいのない話をしながら同じ教室へと向かう。
彼女たち二人を見ても、周りを見ても。何の曇りなく何の特徴もなく、皆一様に軽やかな笑みと共に登校している。
実際、どんなに眠かろうとよっぽどでなければ授業中眠る生徒などいないのだ。寝ていたとしても周りの迷惑にならなければ基本的に教師も周りの生徒も放置。その代わり授業に遅れたとしても、あくまで自己責任。
「おーい、二人ともー。今日の化学レポート書いてきたぁー?」
少しおまぬけな声がして二人は後ろを振り向く。こうして朝の通学路は賑わいを増していく。
それなりの人数の集団ができて、特別会話に参加せずとも支障のないグループが一時的にできあがる。
間堂操はさりげなく口を閉ざし、自然と沈黙に身を置いていた。
横目で彼女たちを見る。一様に皆大人っぽい。しっかりしていて、わからない人が見れば、制服からいって自分達はただの都立高の生徒に見えるだろう。
でも実際は違う。実際は、結構なお嬢様もいるはずなのだ。
「……」
彼女は冷ややかとも取れる視線で数瞬の間同じクラスメートを見た後、前に視線を戻した。教室はすぐそこだった。
教室のドアを開き、
「…あ、おはよう!」
隣にいたはずのクラスメートの声がわずかに高く、心持き弾むように元気になる。表情を見れば、実際笑顔だ。誰かを発見したようである。
「おはよう」
数人の生徒たちが、前を見て同じような表情をしていたから彼女も前を向く。そこにはまさにお嬢様の筆頭たる、生徒。自身のクラスの委員長がいた。
肩につくぐらいの、黒く艶やかな髪。背筋が綺麗で、スタイルがよくて。何より美人。なのに人当たりはよく、物腰は柔らかい。
近づきにくいようで親しみさえ感じやすく、しかし馴れなれしくは付き合えない。そんな下級生のみならず同年代の少女にとっても憧れ的な存在である、クラス委員長牧瀬莉緒。仕事はできて人望もあって。それを鼻にかけることなく、いわゆる完璧な人である。
(私とは違うな…)
胸の内にそっと浮かんだ言葉は、私自身にさえ無意識のもので。
「間堂さん?」
「あ」
ドアの付近でまだ佇んでいた私を、心配そうに覗き込むその顔があり。
「大丈夫?」
「あ、…えぇ。ごめんなさい」
いつのまにかこんな距離を許したのかとドキドキしながら、自然と振る舞う。
「ならいいんだけど」
最後まで完璧なその人の姿に、深く追及されなかったことにほっと安堵しながら。
「……」
向けられた背中にそっと瞳を細める。
「全く違う…」
誰にも留まらない言葉を、また意識下でそっと呟いた。
***
「それじゃまたねー」
「うん、また明日」
放課後。数人のクラスメートと別れて、間堂操は帰路を一人になる。といっても学校の最寄りの駅にてホームを別にしただけのことであり大概の生徒達はその駅にて友人達と別れることになっていた。彼女の使うホームは、生徒達の使用する線としては少数のものだった。
「……」
都心を一周回るだけのこの路線は、自宅と学校を繋ぐ通学路として使う生徒は、そんなにいない。
騒がしい電車内に乗り込み、彼女は吊革に捕まる。そうやって数駅を通り過ぎて、彼女は本来自分の降りるべき駅が来ても何食わぬ顔をして反応すらしなかった。
彼女が次に足を踏み出したのは、若者が日夜たむろすることで有名な繁華街。
何をするわけでもなくどこか目的地があるわけでもなく。街を適当にぶらつき、暇を潰していればすぐに夕方になり夜になる。
この制服は私立校のものにしてはデザインに特徴がない。ぱっと見では良質の布を使っていることさえわかりはしない。だから大変便利だった。よく見れば、その割には崩した着方をしておらず髪さえ必要最低限いじられてない姿は、制服に反してどこか違和感を感じるかもしれない。
しかしそんなぎくしゃくした違和感も通り過ぎる人にとってはどうでもいいこと。彼女は何食わぬ顔で街を闊歩する。
「ん……?」
きっと彼女だからこそ気づいたのだろう。他の人間ならば気にも留めることなく歩き去るだろう。一瞬、目に着いたシルエット。
「あの制服は……」
自分の来ている制服だからこそ、しょっちゅう集団のその姿を目のあたりにしているからこそ、遠目にしても気づくことができる。
「うちの制服……」
どんなに特徴がなくたって、うちの生徒達は改造したりアレンジしたりはしない。
そして何より来ている服の上についている顔、
「委員長…………?」
美人な委員長。その人だった。
(ちょっとちょっと。ちょっと待ってよ…)
人の事など言えた義理ではないが、ここは正直ちょっと柄の悪い繁華街。あちこちで男は女性に声をかけているし、夜の闇が広がっても全く意に介さないような夜中(よるじゅう)ネオンで眩しい街である。正直日頃の彼女からは想像できないような場所であり、どう説明しても二つは結びつかない。
それと…、
(気になるのは)
美人な委員長。学校では物腰が柔らかい……柔らかくしている。そう感じていた印象は、どうも間違いでもないらしい。今見かけた彼女は、やたらにクールで気高くて、言いようによってはきつそうなイメージさえ与えるような横顔…。
(放っておく? それとも、)
正直同じクラスとはいえ大して親しくはない。むしろ、深追いすることによって、何より委員長である彼女には何か致命的な落ち度になるかもしれない。何より、そんなことするのも知ってしまうのも面倒だ。それに、ただの用事ということも、もちろんある。
(放っておこう)
そう決心したにも関わらず、好奇心なんて強くないはずなのに、私の頭の中は今さっき見かけた委員長の事ばかりだった。
『大丈夫?』
今朝の、声をかけてくれた彼女の姿が過る。何の穢れもない、本当にお嬢様という人だった、…………のに。
心から気にかけるような表情が、脳裏に染み付き、痛い。
「ち、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよっ……」
何度目かになる言葉を、今度は口に出して呆然と呟いていた。そんな気なんてなかったのに、勝手に追いかける足は彼女の姿を決して見失わず、適当な距離を開けてたどり着いた場所は、なんと――
目の前で、委員長の後ろ姿が僅かに地下に差し掛かった鉄扉を押し開く。
「な、なんで……。なんで委員長が…………」
心臓が、激しく飛び跳ね体中が動揺に喘いでいた。混乱が頭を占め、まるで心臓が飛び出るかと思うほど、鼓動が耳元にまでつんざく。
体から力が抜け、思わず足がよろつく。すんでのところで踏みとどまった。私を客観的に見つめるものがいたら、きっと顔面蒼白に見えただろう。
「どうして、ここを…………知ってるのよっッ………!!」
腹いせに呟くような、舌うちまじりの悪態である。誰にも聞こえないよう、唇をぎりっと噛みしめながら言葉を口中に押しとどめる。
頭の中を、いろんな考えが過った。
(まさか、私がここに来てることを、知っている……?)
(視察に来たとか。それから学校に連絡するつもりだとか)
(それとも、委員長自体に用事があったとか。そんなわけない、か)
(ならどうして。知人が…、いや、そんな)
知らなかったのならこんなに心を乱されなくて済んだかもしれない。そう思えば唇を噛む力は強くなり。
知ってしまったから何かできることもあるかもしれない。けど今さら何が。
何より、知ってしまったのなら、もう遅いのだ。
「なんなのよ……、一体ッッ……!!」
顔をあげ、鋭く扉を睨みつける。そして足を踏み出した。
「…………」
目の前に広がる光景に、理解が追いつかなかった。(なに、これ…)
現実に待ったをかける言葉がまた頭をよぎる。もう何度目だろう。
委員長は、……私の知ってるあのまじめな委員長は、音楽が大音量で流れるホールで、大して自分と年の変わらないだろう少年少女達と、思うままに体を揺らし、笑いあっていた。
「委員、長…………」
その笑顔が、まるで霧の向こうに霞むようで。知ってる人なのに、知らない人がいる――
呆然と、立ちすくむしかない。
そうしていれば、ごく微弱な声で誰にも届かないような呟きだったはずなのに、委員長は、何かに引き寄せられるようにこちらに振り返ろうとする。身を隠そうなど、もう力の抜け切った私の頭にひらめくわけもなく。
「……………………間堂、操…」
大音量の音楽。人の喧噪。きらびやかな照明。それらが全部、時間を止めて。
聞いたこともないような、冷たい声で、そうつぶやくのだった。
………
…
翌日の学校で。見かけるのはいつものあの人だった。
今日だって、いつもと変わらない風景。朝の通学路を行き、クラスメート達と出会って、何気ない会話をして、授業を受けて。
私の姿だって、みんなの姿だって、…………彼女の姿だって。なんら昨日と変わりなくて。…………変わらないはずで。
そう願いつつも、知ってしまった事実と、気まずさはぬぐいされず。
私は彼女を呼び出すのだった。いまだに信じられないという悪あがきな気持ちを引きづりながら。たとえそう信じていたとしたって、何の救いも与えられないであろうに。
「…………委員長」
問いかける声はあまりにもか細く。自分でも頼りなく心細かった。
(まさかまさか。そんな、ばか、な……。そんなわけない。きっとない。でも、あの人は……)
薄暗いフロア、瞬くレーザー照明。あの時胸に宿った心情が今、胸を突く。
校舎裏に呼び出した彼女は、徐々に近づいてきながらその表情を歩みと共に変化させていく。
優等生の彼女から、そうではない彼女へ。普通の彼女から、不適な表情へ。冷たく何かを見下すような顔つきへ。
そうやって目の前まで来た時、すっかりこの人は変わり果ててしまっていた。今、私の目の前にいるこの人は、昨日出会った人だ。
歩みを止め私の前にただ黙って立ちすくむ彼女に、私は中々目線を上げることができない。これではすっかり、いつもと立場が逆だ。
「間堂さん。顔上げて」
「…………」
「……上げなさい。……用件は、どうせ昨日のことでしょ」
はぐらかす気は、毛頭ないらしい。いきなり核心を突く言葉に、私は顔をあげる。
「……」
――数瞬の間、沈黙の中見つめあい、
「言ったりしないで! お願いッ! 絶対にッッ!!」
「!」
「なーんて、言うと思った……?」
その時の、どこか物悲しささえ感じさせるような儚げな笑みが、忘れられない――
激情と寂寥。そのあまりの早変わりに私は目を剥く。
「言いたいなら言ってもいいよ」
「その時にはあなたのことも言っ…………たりしないな。たぶん」
時間の空白を、味わった気がした。確かにこの数瞬、私の中の時間は止まっていた。
「別に……言ったりなんかしないわ」
ようやく紡ぎだせた言葉は自分のものながらひどく心細げで、タイミングを計ることもできず彼女の話す途中を遮るようにしか出せなかった。
「ねぇ、牧瀬、さん……」
あなた、本当に私の知ってる委員長?
いつも学校で、教室で見かける、あの品行方正を人間にしたような真面目で大人受けのいいあの委員長? 成績はいつも上位で、もちろん人当たりもよくてクラスメートからも教師からも頼りにされてる委員長? 優等生を絵に描いたような、悪いことなんて、微塵も知らないような、普通で、それで、それが……。委員長、委員長……。
私が無意識に呼びかけていた言葉に彼女の本来の学校での呼称が入っていたのはきっとそれを口に出すことで改めて認識したかったから。
今、私の目の前にいるのは、確かに、あの牧瀬莉緒――委員長なの?
「なぁに、間堂さん」
心臓が、……ひどく跳ねた。
その言い方はひどくゆっくりとしたもので、嫌になるほど一言づつ確かに発音する声はやけに低く、どこか厭らしい毒気を孕んでいる。
わざと、いつも通りの呼び方をしている……。
きづいたら私、僅かにだけど呼吸が乱れていた。
「……委員長っていうのは私の役割。だけど私自身じゃない」
私の中の戸惑いに答えるように目の前の彼女は静かな笑みを湛えてそう言う。
「ねぇ、こっちを見て」
「……」
私は、もうどこか取りつかれたように彼女の言葉に従う。顔を上げた。
「昨日のこと、よくある二人だけの秘密にしようだなんて別に思わない。言いたいならそうすればいい。私は、あなたが誰かに言おうが言うまいが誰にも話す気なんてない。ただ単に、面倒だから」
「……えぇ」
(私もきっと言わない)
「あ……」
「なぁに」
「……………制服は、やめたほうがいいんじゃない」
「はっ、大丈夫よ。そんなの」
私の言葉に、委員長は一瞬息を吐き出すように笑うと嘲った。
「あなたも知ってるでしょ。いや、あなたなら嫌というほど身を持って知ってるはずよ。うちの制服、特徴ゼロなんだからばれるわけがないじゃない」
「まぁ、そうだけど……」
「…………私、他人に興味ないから、あえて聞かないけど。……あなただって、人に言えない秘密、持ってるでしょ」
見下すような視線だが、真っ直ぐ見詰めてくるその瞳に、私は思わず目線をそらす。(やめて……)そして瞳を閉じた。
いつのまにか制服のポケットに入れられてあった手を、中でギュッと握る。私自身にさえ届かない微弱な音が、手の平だけに伝わる。
……
「それじゃあね」
続けようと思ったのにそれはただ心の中で呟かれるだけで、その機会さえくれず彼女はそう言い切るとあっという間に背を向けてしまった。
「あ……」
(なに……)
声、掛けたいだなんて思ってるの? 私……。引き留めたいと思ってるの、私…?
確かに掛けたいと思ってる、声。引き留めたいと思ってる気持ち。けど、その理由がないじゃない。
遠ざかる背中はあまりにもあっけなくて。容赦なくて。私に僅かなチャンスさえ与える気など全くなくて。
(さよなら)
――無意識に胸に灯ったセリフを私はすぐに打ち消す。ただの別れの挨拶。条件反射的に出たもの。だとしても、この場面でその言葉は、イヤ。
「また、ね」
この次教室で会う時は、また私が知ってるいつものあなたなんだろうか。
あの、いつも教室で出会う、真面目でいい子な委員長なの?
それじゃあ、今見た、姿形そっくりの、性格が正反対な女の子は、誰?
双子? まさか。 そんな話、聞いたこともない。
それなら同一人物ってことになる。あの二人は。
(よくある二人だけの秘密にしようだなんて、別に思わない)
それじゃああの姿を、あなたの身近な人は知っている?
あなたの一番、本当に近い人間。 母親は?
家族にさえ、あの姿を晒している気が、私にはしない。そうしたら――
(二人だけの秘密、ってことに、なるんじゃないの?)
なんだ? いったい。 何か、混乱してきた……。
どこか熱っぽい頭を押さえる。そうして私もその場をあとにした。
…
向こうの角へ消えゆく背中に、私はそっと心の内で呟く。
(あなたにだって、思いもよらない秘密)
あの場所、手の平の感触……
(私にも、ある……)
(目に映るものだけが全てじゃないのは)(私も一緒)
「どうしたの?! 顔色、真っ青よ」
「あ……、大丈夫だから…」
教室に戻り、扉を開けるとすぐそこにいたクラスメートに心配された。顔色が真っ青なのは、自分でも予想がついていた。事実体が冷たい…。
私は軽く手をあげて彼女を制す。まだ気にしてそうだったけど、これ以上は保険委員か日直の仕事だと思ったのか彼女もそれ以上は何も口を挟まなかった。
「…………」
視線を感じて、斜め向こうへ顔をあげる。
誰にも目につかないような死角から、委員長は口元だけで笑っていた。
間堂は顔をそらす。彼女は委員長の事を、苦手から徐々に嫌いになり出していた。
例えればそう、気まぐれな猫のように。
私を惑わすあなたは悪魔か、……。
「大丈夫? 間堂さん。保健室へお連れしましょうか?」
「…………結構よ」
「そう。何かあったら何でも言ってくださいね」
とびきりの笑顔でそう言うものだから、つい私も不愉快に顔をゆがめて彼女を睨む。
でも私がそうしたとしても、彼女はその美しい顔を崩さず、上品に微笑むだけだ。なんて憎らしい。
…
……
朝目覚めて、いくら待っても体に力が戻ってこないのを感じる。私はパジャマのままダイニングへとやってきた。
頭が、ぐあんぐあんする。
近頃では頻繁に出てくるこの表現ももう何度目かわからない。とにかくそれまで数カ月に一度のこの頭痛に似た吐き気も、このところでは異常なほど頻発していた。分布図で言えばそれはこの一カ月に集中過多している。その図形が頭の中に浮かばれてまた一瞬立ちくらみがした。
朝食を用意する傍ら、クローゼットの中の引き出しに向かう。その中の一つを引いて、中に入っている紙の袋の中身を確認する。
もう、そろそろ行かないと……。
こんなに早くなくなるなんて。このところの発作の連続に今まででは考えられないほど早く飲みきってしまった。
元々、通院することは欠かさないことだったけれど、それでも余計にその頻度は増えそうだ。
……
…
夜がものすごく長く感じる。
日中、追いかけられるように過ごす日々と同じ時間が過ぎているとはとても思えないほどの、緩慢とした時間。
暗闇に閉ざされた見慣れた自分の部屋で、時計の針がかちかちと僅かに時を刻んでいるのが聞こえる。
(長い…)
冴え渡った意識はまどろむ闇へと私を落としていってはくれない。
何度目かの夜を超えて、私はやはりいつもの通学路を行っていた。
ようやく学校に辿り着く。
遅刻寸前の閑散とした通学路かと思ったら、辺りには生徒が溢れかえっており腕時計を見れば今がちょうど登校のピークだった。
私も何食わぬ顔をして流れに入る。学校までの列はそんな私を何の違和感なく迎え入れる。
あまりにもそれが自然すぎて逆に私には不自然余りあるほどに感じ、この光景さえもどこか欺瞞にあふれるものに感じてしまった。
昇降口で靴を履き替え教室へと向かう。
階段を登り、廊下を行く。
その途中で、二人の男女を見かけた。もちろん制服を着ているからうちの生徒。
ただ視界に入っただけで自分とは何の関係もないことは言うまでもなく、私は廊下を歩むスピードを緩めることなく進んでいく。
彼女たちからは私の背しか見えない。私にも視界には入らないはず。……なのに私の視界の隅が、彼女たちを追う。やめろって、意識が叫んでるのに。
すれ違う瞬間、二人がどこか思わせぶりな笑顔を一瞬浮かべていたのが目に入っていた。
そしてそのまますぐ近くにあった教室の扉に凭れかかるようにしたと思ったら、あっという間に吸い込まれていくように中へと消えていった――
見たくないものでも、意識したくなくても、目をそむけているつもりでも、勝手にその瞬間というのは目に飛び込み脳に伝わる。
私はもうとっくに通り過ぎているその地点で見た光景を、必死に頭を振って追い出そうとする。その教室は資料を保管しておくのみの一日中カーテンで閉め切られている暗室だ……。
「……………………うっ」
喉を這い上ってくる何かに咄嗟に口元に手を添える。気持ち悪い……。
何をする気なの? 朝っぱらから、そんなところで……。気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪いっ――
「あ……」
足もとがふらつく、と思ったら私の視界は既に白く霞んでいて、改めて足がぐらつく。渦が頭の中に巻き起こり、真っ直ぐ立ってられない。
さながらそれは千鳥足のようで。でも決定的に違うのは首から上が自分でもわかるほど寒いぐらいに冷たかった。
「あぅ」
ぐあんぐあんする……。目の前の光景が、すべて歪んでみえる。重力が右に左にひっくり返ったようで、私はそれに振り回されどこか正常な位置なのかさえもわからない。きっと、私は今の状態を聞かれたら医者にそう答えるだろう。
「大丈夫?」
…………。今、何か聞こえた?
聞こえた気がするけど、あまりにも遠くてそれが私なのかどうか。
「間堂さん」
それは、私の名前だ。聞こえたらしい方向である後ろに振り向いてみる。
「大丈夫?間堂さん」
「…………………委員長」
「顔、真っ青よ」
朦朧とする頭が、すぐに彼女の存在を理解させてくれなかった。何せ私の目にはまだ彼女は白い霞の中にいる。
「貧血? 保健室行く?」
何なのよ、一体……。同じセリフなのに、この前の時とはまるで違う。
心底心配してるような口調と目の前の覗き込む顔に、私は気のせいだとしても余計に気分が悪くなる気がした。
「…………大丈夫」
「そう? 授業始まるまで、ベッドで休ませてもらったら?」
「ありがとう。でも、本当に大丈夫だから」
優しくしないで。
キッと、睨みつけた。
「そう? …………」
まだ腑に落ちないようだったけど、それでも納得してくれる。(あんた、誰よ……)
(不敵な笑みを浮かべて遠くで嘲笑している方がよっぽど『らしい』)
徐々にしっかりしてくる意識。私の腕には、彼女の手が添えられていたらしい。今はゆっくりと離れていくところだった。
……きれいな手。何の罪も知らないかのような。穢れなき白く美しい手。けれど本当は、真実は――
この人は、私の知ってることの半分でも、はたして知ってるんだろうか。
「無理はしないでね」
髪は長くて艶やかで。同学年に見られるような子供っぽさのない、洗練された頼りがいのある、生徒。大人からも、生徒からも評判のいい、そんな美人な少女。
「えぇ」
もし私が、彼女と何もありもしなかったなら、
私とは生きる世界が違う。そう思いいらつきもしただろう。
こんな人もいるんだなと、どこかで安心もさせてくれる人だったかもしれない。
けど違う。今は違う。
「猫、……かぶってるんじゃないわよ」
ぽつりと呟いた言葉の後、場がシンと静まる。
何も言い返してこない牧瀬莉緒――委員長。どうでもいい。今度は頭が割れるように痛い……。
(猫、かぶってるんじゃない)
それって、相手に言い放った言葉にも聞こえるけど、私自身に対して言ったようにも、聞こえるよね――
今だに何にも言い返してこない。なのにまだ目の前にいるらしい。不気味。
「あっ…ち、行って……よ……っ」
口が勝手に動く中、目の前の影が動いたのがわかった。
「間堂さんて、本当に不器用ね。…………愛おしいぐらいに」
「!…………」
「でもそれじゃ、生きぐるしいでしょ。とても」
「やめ、て……」
私の足が、無意識に後ろに退く。自分では見えないけれど、表情が震えている気がした。頬を、取られる――
「怖い? 私のこと。誰かわからない?」
整った顔が、そこにある。大人っぽい端正な顔が、力を抜いた優しげな表情が、そこにある。
私は力の限り頭を左右に振る。言葉か何かを発すればいいのに、まるで幼い子供ように。
ただひたすら、それを否定したい、だけの。
そんな私の歪に震える頬に添えられた手が、そっとあごにずれる。(あ……)「え?!」
ぐいっと持ち上げられ、瞳がのぞきこまれ――(ち、近い!近い!)至近距離に、彼女が――
(き、キスされ……)
「……ん?」
ぎゅっと目を瞑った瞬間、大きな鐘の音と小さな呟きが聞こえる。始業のベルだった。
「あ、…………」
もうこんな時間なんだ……。ほっとして息をつく。目の前の人は……つまらなそうに廊下の向こうを見ていた。
「ったく、無粋ね……」
「……ぁ」
その瞬間、遠くで彼女の声が聞こえた。目の前にいるはずなのに。……頭が、痛い。くらくらする……。
再び襲いだした頭痛に重たい頭を抱えれば、やたらと耳に響く戸を開く音がしてそちらに目を向け――
「あっ……、……」
今さっき、の……。
今さっき見た、二人。ついさっき(随分前の事に感じられるけど)私がすれ違った二人。暗室に、消えていった二人……――
体が、冷たい……。血の気が、引いていく。
「…………変なとこ真面目よねー。ちょっと間抜けじゃない? …………ちょっと」
「あ……ぅ…」
「あなた……、…………あっ!」
委員長が私を見ていた。私はこみあげてくる吐き気に口元を押さえていた。頭は蒼白で、冷たくて。体は重く、目の前は歪んで見えた。
耐えきれず、私はそのまま駆け出す。生徒が全く消えてなくなった廊下をただ走り抜けた。
「ちょ、こら! 待ちなさいよ! 操!」
「牧瀬さん?!」
「あ、…………先生、おはようございます」
「おはよう。一体どうしたんですか。 今もう一人廊下を走っていった気がしますけど」
「すみません。彼女同じクラスなんですけど、どうも具合が悪いみたいで。私が保健室につれていきますので担任によろしくお伝えくださいませんでしょうか」
「え、えぇ。わかりました。ではよろしくお願いしますよ」
「はい」
何の疑いも持たず、隣のクラスの教師は彼女を信じる。こんな時、日頃の行いが物を言うものだ。
真面目一辺倒の面をかぶりつつ彼女は胸中で冷静にそう呟く。
さて。タイミングがいいんだが悪いんだか。教師への伝言のせいでちょっと距離ができてしまった。彼女はどこへいったかな。
でも案外平気なもの。
始業のベルが鳴った後の校内では、ほらこうして耳を澄ましてみれば…………わかるもの。
頭上のかなた向こうから、トントントンと微かな地面を蹴る音が響いてくる。
「屋上か」
さぁ彼女を追いかけよう。一体彼女は何をするつもりなのかな――
「…………ハァッ…」
一瞬の閃光の後に、突き抜ける青空が目の前に広がる。
屋上にやってきて私は……。
体調は最悪、加えて頭を悩ますような日々が連日続いたせいで私は、正常な判断を下せなくなっていた。
制服のポケットに手を突っ込み、いつもの私なら考えられない行動をとる。
ビニールパックを取り出すと、慌てながら中の白い粉を掌に落とす。それをぎゅっと握りしめる。粉が、僅かに空に飛んだ。
「はぁ、…………はぁ…」
苦しい…。
コンナコトシテモなんの救いにもならない。ソンナコトハわかっていた。
握りこぶしのままの手を口元に近づけ、手が震える。
(ちょっとちょっと)
ここは学校だよ。なんだよこの震えは、タメライ傷かよ――
やめなよそんなことしても、なにもならない。――もう楽になりたい
「う、うぁ…………!」
ばっと空に飛ばした。今までにも見たような光景。白い粉が真昼の屋上に飛ぶ。
「はぁはぁ…………もうダメ……。私…………」
「前言撤回。大いに踏み込ませてもらうわ」
「!」
突然聞こえた声に、私は体を震わせ顔を覆った態勢のままそちらに振り向く。
「秘密は共有するものよ」
「牧瀬莉緒……」
つかつかと、後ろからやってくるのは委員長の姿だった。
「それ、…………使う時は私も一緒だわ」
「な、何………バカな事……!」
表情が見えなかった委員長が、顔を上げ同時に私の手首を掴んだ。
「……!」
「わかった? 秘密を共有するというものは、そういうことなのよ」
「っ……! 馬鹿なこと言わないで!!」
近い! 数センチしかないほど近づいた互いの鼻先に、私は勢いよく体を翻し手首から逃れる。そしていい加減、私の中にわだかまっていた不満が……爆発した。
「あなた、わかってるの?! これが何か!! あなたが思ってるような……。いえ、思ってるよりもずっと……ッっ!!!」
「わかってるわよ。馬鹿じゃない。それよりもあなた、それ使ったことあるの?」
「え? ………………」
「…ならいいわ。それならなおのこと。使うならその時は私も一緒。わかったわね」
「…………わかるわけ」
「わかったわね」
「っ」
命令口調に変わった言葉と、上から睨み据えるような視線に、私は思わずたじろいでしまう。
「…………、なんで、……なんでそんなに私に関係してくるのよ!!! お互いの秘密だって、こうして……。こうしてたまたま知ってしまっただけのことじゃないっ!!!!!」
「別に私の秘密は、ばれたって構わないわ。でも、あなたのそれは…………どうでしょうね?」
「っ……、なんて、奴なの……」
「あぁ、誤解しないで。私は何かを知ったって知らないのと同じよ。私の中では」
「でも。…………一人でそれを使ったら、許さない」
「わかったわね」
「くっ……」
幼い子供が本気で母親に叱られた時のように。背中に冷汗が伝う。『怖い』
「…………あなた、わかってるの?! あなたもこれ、使うことになるかもしれないって。そう言ってるのよ」
「えぇ」
「知ってて知らないふりをするということを、…………わかってるの?!」
「えぇっ」
「じゃあなんでそんなにかかわってくるのよ?!」
「あなたの望む答えは?」
「っ…!」
離れていた距離が一瞬で縮められ、そして顎を掴まれた。そうしてまた数センチの距離に顔を近づけさせられる。
「『あなたのことが心配だから』」
「っ」
「そうよね?」
「……私を馬鹿にするのも、いい加減にっ…!」
「いいこと。私はあなたとの関係が愉快なの。おもしろいのよ。興味深い。それ以上でもそれ以下でもないわ」
「……」
「望む答えを用意してあげる。でも私の口から出る言葉はほとんど真実とは限らない。…………呪うなら私に気に入られた事を呪うことね」
「…………えぇ、本当に」
吐き捨てた。
ちょっといいかと思ったらこれだ。なんて食えない奴…!!
その会話を最後に、屋上には沈黙が戻った。下では、今日も教師が講釈を垂れている……。
長く感じた沈黙に、私の中の意気はすっかり消沈していた。何だかいきなり情けなくなって、悲しくなって、力が抜けていく。
「お願いだから……。…………これ以上、関わらないで」
「……」
「あなたの気まぐれに付き合わされるなんて、そんなの……っ」
私の視界に、足が踏み込む。「え……」
唇に触れた何かに、驚いて顔をあげると、そこには離れていく委員長の顔があって。
「また一つ、秘密、できたね」
「………な」
状況が把握できず、呆然としていたがようやく事実を理解する。途端に顔が熱くなった。
……そうして、何か緊張のようなものが、体から抜け落ちた。
「あはっ………。あははは、ははははは……」
「……」
委員長はいきなり笑い出した私を、静かに見守っている。私はひとしきり笑った後、彼女に向き直った。
「…………あーあ。もう…………わかったわよ。…………あなたのこと、……わかったわよ」
「なにが?」
「もう…………真面目に向き合わないことにする。肩の力、抜くわ」
「…えぇ。それがいいでしょうね。きっと」
「全く。…………ふ…ふふ…」
なんか突然どうでもいいような気がしてきて。私は屋上の真っ青な空を仰いだ。
気まぐれな猫に、全力で付き合っていたらただ思いっきり振り回されるだけだ。
「はぁ。…………いいわ。秘密を、共有する」
「OK」
「ただそれだけの、関係よ」
「もちろん」
そう言って笑う委員長が、あまりにも爽快な笑い方をしていたから。
私もつられて笑う。友情だとか別になんでもいい。言葉で表現できない何かで、この人とつながりあったのは確かだった。
それだけで、……もういいや。
……
…
「キス、返してよ」
「それ無理。どうやって返すの。もう一度するの?」
「結構です。……私の唇を奪った対価は、大きいよ」
「それは光栄だわ」
ep1 end
UP 2012/11/8
無断転載・引用禁止
Copyright(C) nokizaka All Rights Reserved