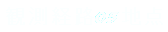ss
cross
……良かったぁ。
何だか彼と会ってからお姉さんの様子がおかしかったから、気づかない内に気に障ることをしてしまったかと思った。
彼と会ってから、少しの間捕まってしまい、あげくの果て彼の話ばかりでは不愉快に思って当然だ。
私としては、ただあらぬ誤解を解きたかっただけなんだけど、それが思わぬ方向に行ってしまったら、何の意味もない。
嫌われたくない、なんて、なんて幼稚なそれこそ学生的な考えだろう。
今まで私は、そういう事を考えられないからこそ周りから浮いてきたはずなのに。
さっきまでの私を思うと……思わず頬が熱くなる。
あんなに、まるで幼い子供のように手を掴んだまま立ち止まり、必死になって訴えるなんて。
……冷静に考えてみれば、私とお姉さんはそれこそ他人同士な人間ではっきり言ってなんの繋がりもない。
公の場で付き合わざるを得ない関係でもない。これから先もそうなる可能性なんてない。
だからこそ、……
繋がれた手をふと見る。
何の繋がりもない、私とこの人。
この手を離してしまえば、今朝までのただ電車の扉に凭れる私と、反対側の扉付近でつり革に捉まる彼女に戻ってしまう。
せっかく、僅かな勇気といくつかの偶然が重なってこうして今があるのに、白紙に戻ってしまったらまた見つめるだけの関係に戻ってしまう。
…何言ってるんだろう、私。
……今日限りの関係って、言ったのは私なのにね。
結局再び街に放り出された私たち二人。
しかし、いかんせんお互いに用事なんてないのだから、どうにもこれからの行動に困る。
まぁ例え用事があったとしても、付き合わせることなんてできないのだけど。
(どうしよう)
自分から誘っておいて、何をしようかここに来て迷っていた。
そもそも自分は普段からあまり外出なんてしない。
だから定番のコースがわからない。
友人と――数少ない友人と、出かけたりする時はどこに行ってたっけ?
カラオケ?映画?ショッピング?
なんとまぁお決まりの選択肢だろう。けどほかに思いつくものも中々出てこない。
「どこ行きましょうか…」
「私は、どこでもいいけど」
思わず思っていたことを呟いてしまった私にお姉さんはそう返す。
東京はあまり詳しくないし。こう付け加えられてしまったら元も子もない。
……私は一応東京の人間だけど、実はそんなに東京の定番スポットみたいなものに詳しくない。
加えて付き合いの悪い人間だから、レパートリーまで少ない。
こんな時に今までの自分の性格が祟るだなんて。
思わず歩きながらうんうん唸るしかない。
「別に、……はっきりとした目的地はいらないんじゃない?こうして、目についた所に入ってみるとか」
「あ、そうですね」
「デートとか、しないの?」
「しないです。友達と来る時だって、適当に過ごしてるだけですから」
「そうなんだ」
でも、私たちはまだ知り合ったばかりだから。
他人と知人の、狭間に位置しているようなものだから、そんなラフな時間の過ごし方はできない。
「そんなに、気張らなくていいから。楽にしてくれて、大丈夫だから」
「あ……すみません」
「ううん」
「私、実は人に連れられてきたりする事多いんですけど、自分からリードする事ってあまりないんです」
「そうなんだ」
「だから、いざどこか行こうってなったら、どうしたらいいのかよくわからなくて」
誘った手前っていう何か義務感みたいのを感じてしまった。
いつもなら、こんなこと全く感じたりしないのに。
「楽しく、過ごしてほしいんです」
「え…」
「あ、いや…。こっちの話…です」
……
…
時折見え隠れする十代らしいまだまだ幼い表情と日頃の大人っぽさへのギャップに、まだ慣れることはできない。
変なところ大胆だったり、さりげなくスキンシップしてくるのに、また変なところで緊張して困っている。
正直、もっと引きづられる形になるかと思ったけど、固くなっている彼女に手を差し伸べる形になっている。
考えてみればまだ十代の女の子に、自分よりも年上のお姉さんをエスコートしろだなんて、きつい話だよね。
時間が経てば経つほど、私はこの子の事を知らずに色眼鏡で見ていたような気がしてきた。
何より、私だって一応大人なんだし、少しくらい年上っぽいこと、したかったんだよ――
「それにしてもすごい人だねぇ。平日なのに」
「もうお昼過ぎですからね。ここっていつもこうなんですよきっと」
進む通りも中間辺りまで来るとさすがに人の数が多くなってくる。
どの人もまぁ街の雰囲気に合ったお洒落な服装の人間ばかりだ。
暑さも午前中より増してきてるし、若干まだ慣れない人ごみに息苦しさも覚えてくる。
「こっち行きましょう。こっちにもお店はあるんですよ」
「え、あ、うん」
唐突に腕をとられ人ごみから避難させられる。
裏通りに着てみれば、そこは格段に人の数は減るが逆に個人店が軒を連ねる。
時折カメラの前でポーズをとっている人がいた。
「あれって撮影?」
「さぁ。でもたぶんそうでしょうね」
表通りの喧騒はかすかに聞こえるだけで、こちらは落ち着いて静かなものだ。
「まぁ、もう少し行くと、また表通りに出ちゃんですけどね」
カラオケなんて行かなかった。
洋服もウィンドウショッピングで済ませるだけだった。
アクセサリーショップに、多少寄るだけ。それ以外はただひたすら街中を歩いての散策だった。
会話は尽きない。はたから見たら、とても仲のいい友人同士か知り合いに見えたんじゃないだろうか。
日が暮れ始める。
それでも永遠にこの時間が続きそうな気がしていた。
終わりなんて来ないって。
傾いていく日に目が向かないぐらい、確実にそう思えていた。
小さいクレーンゲームで、小さいキーボルダーを一つ手に入れて、私たちは今喫茶店の外で向かい合わせに座っていた――
日はもうとっぷり暮れていた。
「お姉さん…」
「…………」
帰りたく、ないなぁ。
でも言えない。言っちゃいけない。
「…………」
私が黙っているものだから、結局彼女も押し黙っちゃう。
テーブルに片方だけ肘を突いて、その指に先ほどとったクマのぬいぐるみのついたキーボルダーを下げる。
これからきっと、辺りは暗くなる。
もう既に、夕飯時だ。
暗くなったら、明日だってある。『明日』だって…――
何言ってるの、私……。
『今日限りの関係』だって、そう言ったじゃない。
だからこんなに……――
前を見れば、彼女は『彼女』の姿に戻っていた、ような気がした。
出会った時に抱いたような印象。大人っぽくて、垢抜けていて、綺麗な子。
手持ち無沙汰にキーホルダーをいじる表情は、どことなく気だるそうで近寄りがたい。
……なぜか、胸に焦燥感が迫る。
それこそこの子の事、『今日限り』でしか知らないし、他の顔はわからない。
でも、……今日知った私にとっての彼女、以外の人になってしまうそんな焦り。
鮮やかだった周りの風景が、途端にまたセピア色に変わっていってしまう。
それは、一概にも辺りが夕暮れ時になったからだけのせいではない。
気づけば世界が彩り鮮やかになっていた。それまではきっと、……色さえなかった、褪せた世界。
本来なら、迷う必要もないこと。
私たちは、昨日までの日常に戻る。ただそれだけのこと。どうしよう……
「うちに、来ない……?」
「え?」
「うちに、寄っていかない?」
「…………」
初めの言葉は少し震えた。
二度目の言葉ははっきりと告げられた。
聞き逃しなんて、ないと思う。
言ってしまうと、何だか随分大きく構えたもので、彼女の表情の変化をじっと追ってしまう。
そうとう、迷っているみたいだった。
心の中の困惑が、見て取れる。
困らせてしまっている。
そう思うと今の自分の発言を悔やみそうになるが、そうまでして押し通そうとする自分のわがままさも感じていた。
「わた、し……」
その続きは、断ろうにも承諾するにもどちらにも続きそうなニュアンスだった。
寸前まで、迷っているのが目に見える、気がした。
私は、彼女が困るのを知っていてこんなことを言っている。いじわるだ。
「寄る、だけなら……」
そう彼女の唇がゆっくり動くのを、どこかふわふわした視界の中で見つめていた。
――――
「っ、お姉さんっ、大丈夫、ですか?」
「うぅ…」
「ここで、…いいんですよね?」
「うぅん…」
なんてこと……。
もう1人では満足に立つこともできない。
あのタクシー…よくもあんなひどい運転をしてくれたものだ。
更に喫茶店で出された飲み物と、お菓子。どちらかに隠し味としてお酒が含まれてあったのか、それともアルコールがちゃんと
飛んでなかったのかわからないけれど、口にした後であの独特の香りが舌についた。
二重のトラップのおかげで、こうして朝からの不調も舞い戻ってきてしまっている…気がする。
「うぅぅ」
「しっかり。ここで、いいんですよね?」
情けない…。
支えがなければ、一人ではもう歩けない状態だなんて。
そして、体調不良の視界に唯一安心できる見に覚えのある風景と景色が頭上に広がっている。
「そう…、ここ……」
夜の帳が落ちてきた景色にそれがそびえる。
私の東京での一人暮らしを営むマンションだった。
***
どうにかこうにか、話を聞きながら全くの初見にあたるマンションを突き進んでいく。
今は、管理人さんはもう帰ってしまったようだった。
おかげで人目に触れることなく、この清潔そうな綺麗なマンションを進むことができた。
「ここ、ですかぁ?」
「…………、たぶん、そう…」
エレベーターに乗って何階かのフロアで降り立ち、僅かな説明を元に廊下を進む。
たぶん、ここだろうという場所でドアの正面に立ち、お姉さんに尋ねてみてもまた随分頼りない返事が返ってきた。
「えーっとそれじゃ、鍵、鍵どこですか。部屋の鍵」
「鍵はぁ…」
「……っと!」
お姉さんに部屋の確認を取った後、半ばなだれ込むようにして二人で玄関に入った。
本当に力の抜けた人間っていうのは私一人ではさすがに持て余すほどで、感慨深げにお邪魔するなんていう余裕はなかった。
「うぅ…」
「大丈夫ですか?」
既にぐったりしているお姉さんの体をあともう少しと多少引きづりながら廊下を進む。
部屋は暗かった。
少し進み、開けた場所にたどり着いたようなので薄暗い中、壁を探る。
これかな…
パチッ
指に引っかかった突起物を試しに押してみるとそれは部屋のスイッチだったようで、途端に部屋が明るくなる。
「気持ち悪いぃ…」
「あ」
そうこうしている間にお姉さんは自分の部屋のソファを見つけるとよろつきながらも真っ直ぐに近づいて行き、……倒れこんだ。
「あらら…」
なんとまぁ。
私が女だからいいけれど、スーツに皺が寄るのも多少捲れるのもお構い無しだ。
二人用ほどの大きさのソファに、身をちぢ込ませるようにして納まっている。
にしても……。
じっくり部屋を眺める余裕なんてないけど、それでも辺りを見回してみる。
ここは、お姉さんの香りで一杯だった。
甘くて、優しい匂いだ。
そういえば、お水はどこだろう。
蛇口は?冷蔵庫は?
できれば、こんな時は常温の水の方がいいと思うけど、蛇口の水そのままは大丈夫だろうか…。
浄水器でも、ついてればいいんだけど…。
それにグラスは…。
そんなことを思ってきょろきょろしていると、後ろから小さく声が聞こえた気がする。
「大丈夫ですか?」
振り向きざま声を掛けてみても、お姉さんはただ苦しそうに眉を潜め固く目を閉じているだけだった。
「うぅ……、ごめんねぇ…」
すっかりダウンしていながらもぼんやりとそう呟くお姉さんに私はつい笑ってしまう。
「いいんですよ」
――――
「お姉さん…」
「うぅん…」
私の呼びかけにも目を瞑ったまま苦しそうに唸るだけのこの人に、私はつい笑みを零しながら何を思ったか静かにその唇に触れた。
触れるか触れないかの微妙なタッチで、乾いた唇の上を人差し指が辿っていく…。
「ん…」
お姉さんの口から、震えた吐息が漏れる。
「………」
別にどうこうしようなんて気はなかった。
今の漏れた声にだって、何も感じない。
私はただ、ソファに寝るお姉さんの顔元に、床にしゃがんで腰掛け見つめる。
大人っぽいと感じる時が今日一日で何度もあった。でもやっぱり、こうしていると初めて会ったときと同じ印象だ。
「可愛い」
「んん…」
こんなこと、起きている間には絶対に言えないけど。
「聞いたら、……怒りますか?」
「……すぅ」
返事はただ安らかな寝息のみ。私はまた小さく微笑む。
もし可能ならば、怒った顔も見てみたいな…。
ずっと一緒にいたい。ずっとそばにいたい。
そう他人に対して思ったのは、お姉さん、あなたが始めてですよ。
名前も知らないあなたの、
大切な人になりたいんです。
名前を知ったらそう、今日のルールが崩壊してしまう。
「だから聞けない…」
私たちを繋ぐものは、まだない。
こうして側にいることしか。
前にかかる髪をとって後ろに流す。前髪を軽く撫でた。
「ぅん…」
「………」
寝てる相手に私ったらなんてことを。しかも相手は私よりも年上の社会人のお姉さんなのに。
―――
お姉さんから目を離して所在無さげに部屋を見回す。
壁時計が、僅かに音を発しながら時を刻んでいた。
それ以外は、まぁ静かなものだ。
典型的な1人暮らしっていう、どこか無味簡素とも取れる雰囲気の部屋。
照明はどことなく薄暗かったし、カーテンも閉められている。
窓の向こうから、規則的な電車が走り去っていくような音が聞こえる気がするけど、それが過ぎ去ればまた静寂に包まれる。
雑然と置かれた家具が、余計にここに住む人間は1人なんだとなおさらに感じさせる。
お姉さんに目を戻す。
寝顔はとても幼い。子供のように、疑いを知らないような無垢な寝顔。
ギシっと音を立てて、ソファに肩肘をついて見つめる。
…何も感じないなんて嘘。
ううん、今この瞬間に、今さっきまでの言葉が嘘になった。
熱いような、それでいてこの胸を締め付けるような息苦しい切なさは、今までに感じたこともあるような気がするけど、たぶん初めて。
「………」
顔が僅かに、近づく。こんなに近づくと、言っちゃいけない言葉が口をついて出てしまいそうになる。
…我慢我慢。
近づきすぎた距離を、後ろに退いて離れる。
私……
てっきり自分には、この世界に居心地のいい場所なんてないと思ってた。
そもそも居心地のいい――自分の居場所――なんてものは、存在しないって。
私のいる場所は、どこもどことなく違和感を感じる、気持ちよくない場所だけだったから。
でも気づいてみれば単純なもので、
結局どれも私にとって『居心地のいい場所』じゃなかっただけなんだ。
だから居心地の悪い思いをしてる。居心地の悪い場所。
なんだ、そっか……。
私自身に、何か問題があるのかと思っていたけれど、そうか、そうじゃなくて、もっと根本的にもっともっと手前の初めの部分で躓いてたんだ、私。
居心地のいい場所に行けばきっと、居心地のいい思いができたはずなんだ。
今まで、それにも気づかず自分の毛色ばかり気にしてた。
でももう、遅い――
「もう、ゲームオーバーかな…?」
部屋の壁時計を見上げる。
お母さんの帰りは遅いけど、そろそろ帰らなきゃまずい頃になる。
ずっとこの寝顔を見つめていたいけど。
戻らなきゃいけない日常がある。
「…………」
指をつつつと首筋に移動させる。その時お姉さんの表情がゆがみ、びくっと体が震えた気がした。
そのまま私の手は顔の前に置かれている彼女の手に辿りついた。
手のひらが上になっているその手に、私はぎゅっと自分の指を絡ませた。そしてふっと解く。
やりきれない気持ちで立ち上がった時だった。
「……え?!」
立ち上がろうとしたけどできない。
膝を突いて体重をかけたところで、何かに引っ張られる。
解いた手は再び握り締められていた。
「行かないで…」
「………おねえ、さん…」
「帰らないで」
見れば、お姉さんの目は開かれている。
思っていたよりもずっとしっかりした眼差しをしていた。
意思の強さを思わせるけど、具合のせいなのかわからないけれど瞳は濡れてもいる。それに思わず胸が高鳴る。
「お姉さん、……もしかして、ずっと起きて…」
「そんなこと、どうだっていいの…!」
「…………」
私を見ていたその顔が、ソファにうずめられる。
それでも手は、強く握り締められたままだった。
「お願い、…………他人に戻らないで」
「!…………あ、」
顔を上げ、体を起こし、私の体が前に引っ張られる。
微妙な態勢だったものだから、あっけなく私の体は前に崩れる。
心臓が、これでもかってくらいドキドキしてた。
「おねえ、さん…」
「…………」
私の体に、お姉さんがしがみ付いている。
服越しでもどこか熱さの伝わる温かい体温と、柔らかい体。
香水じゃないような、でも甘い香りが髪から鼻腔をくすぐる。
0距離で密着する感触に、思わず身震いしてもう全て投げ出すように目を閉じてしまいそうになる。
それでもかろうじて意識を保って目を薄く開けていれば、お姉さんがぎゅっと顔を服に押し付け、両腕は脇から肩へと回され
私の体を引き寄せていているのが目に入る。
まるで子供みたいな抱きつき方に、ほんの少しだけ笑みがこぼれたのは秘密。
1DKの部屋に、夜の喧騒と微かな街のざわめきが聞こえた気がした。
「いいんですか……?」
「……」
「ずっと一緒に、いても……」
「…っ、いいの!ずっと一緒にいてって、さっきから………!」
もう限界。
たまらずに胸から顔を上げるお姉さんに、私は瞬時に顔を近づけた。
「むっ…!」
抱きつき方も可愛いと思ったけど、顔を上げた瞬間の顔もまさに幼い子供のようで、微かに充血し涙で濡れた瞳。
条件反射のように、ただ突き動かされた私の体がお姉さんの体をぎゅっと抱きしめる。
息苦しいほどに抱きしめあい、唇が彼女を求めた。
こんなに人を求めたのは初めて。こんなキスをしたのも初めて。
相手は女性だけど、不思議とその優先順位ははるか遠くだった。
私を突き動かしたのは欲望。私はこの人に欲情していた。
「……っはぁ…」
どのくらいの時間そうしていたのかわからないけれど、しばらくして唇が離れる。
お姉さんの瞳は未だ濡れたままだったし、今は顔もとろんとして上気していた。
それは私も同じだったと思う。
頬を叩かれるとか、突き飛ばされるとかはなかった。
拒否される、ってことはなかったみたい。
「ずっと一緒にいます」
「……」
「ずっと、……側にいます」
「………」
こくんと、お姉さんが頷く。けど、
「だからって、…………こんな急にキスしなくったっていいじゃないぃ!」
「あ、……すいません」
怒ったような笑うような、それでいて涙をすする声が聞こえる。
涙を指で拭うその人の体を、もう一度近づいてそっと抱きしめる。
そして私はただずっと、その背中を撫で続けた――
「大丈夫ですか?お姉さん…」
「うん…」
どれぐらい経ったのかわからないけど、部屋の壁時計がただゆったりと時を刻むのを感じながら、しばらくしてお姉さんに語りかける。
手首で涙を拭うお姉さんのしぐさは、出会った時よりもさらに幼く見えた。
「ねぇ…」
「はい?」
「…………その『お姉さん』っていうの、やめない…?」
「え…?」
お姉さんの顔を改めて見る。するとお姉さんは怒ったようにふいっと顔を背けてしまった。
微妙に、顔が赤らんでいる。
「おねえさ……」
「だめ!」
「う………、…………っていうか、お姉さんずっと起きてたんですか?」
「え」
明らかにその『え』には濁音が含まれている。
「何ですか、その図星みたいな反応は」
「え、いいいや、あのその…」
わざと声を低くして詰め寄れば、焦ったように目を泳がせる。
「ずるいですよ、寝たふりなんて……」
今度はこっちがすねる番だった。
「だって…」
「だって?」
「……ドキドキして起きられなかったの」
「あ…」
赤い顔で告白してくるものだから、二人してそこで赤面する。
考えてみれば、恥ずかしいことをしていたのは自分なのだ。
「ねぇ…」
「は、はい…?」
「お願いだから、そのお姉さんっていうのやめて…」
「あぅ…、………はい」
甘えるような言い方に、思わず腰が引けてしまう。
困って固まっていると、胸にお姉さんがもたれかかってくる。
「私の、名前は……」
「…………」
「比嘉、那々子」
「あ…」
確か、沖縄出身だっけ…?
さすが、本土ではどことなく珍しい苗字だ。
名前を聞いてしまえば、彼女が沖縄の人だなんていうのはどことなく察しがつきそう。
「あなたの、名前は?」
「私の、名前は……」
名前を言うだけでこんなに緊張するなんて。
「瀬利灯子」
「灯子…」
名前を聞いて、お姉さんが静かに微笑む。
「変、ですか?」
「ううん。…………ようやく名前がわかって、嬉しいの」
どうしよう。
胸の中に顔をうずめたまま顔を左右に振る仕草に、やたら胸がときめく。
ただ名前を教えあうだけなのに、やたら甘くて切ない時間が流れてる気がする。
安心するような気もするけど、どことなく胸が痛い。
「んん…」
「……」
やっぱり大人の女性なのかな…。
胸に顔をうずめていた姿勢のまま腕が背中に回されきゅっと抱きつかれる。
というか……、実際はこんなに甘えん坊なんだ…。
今日一緒にいて、そんなそぶり全く見せなかったから、私は戸惑い緊張して成すがままになるばかり。
どうしよう…。
「今日…」
「はい…?」
「今日、帰らなきゃダメだよね…」
「ぅ…」
あぅ…。そんな言い方されちゃうと、帰りたくなくなるんだけど…。
「ふふ。大丈夫。私だって大人なんだから。そこまでわがまま言わないよ」
「はぁ」
そこで胸を張られても。
それに、
まだもう少し、わがままを言っていてもらいたい気もする。とても、居心地がいいから。
……
…
「それじゃ、そろそろ私行きますね」
玄関に降り、靴を履いた所で彼女はそう言って振り向く。
「うん…………、あ、灯子ちゃん」
「!」
?
名残惜しくて、なんとなく背中にかけた言葉に、ドアノブに手をかけた彼女の体が傍目にもそば立つのがわかった。どうしたんだろう。
「どうかした?」
「い、いえ…。その、『灯子ちゃん』なんて呼ばれたの、久しぶりで…」
子供の時以来です、って付け加えられる。
振り向いた顔は、真っ赤だった。
「そうなんだ…、日頃は、なんて呼ばれてるの?」
「日頃は苗字です。私の名前って、苗字も何か名前っぽいから…。たまに名前で呼び捨てにする人もいるけど」
「そっか…。……確かに、『瀬利』って名前みたいだもんね…」
「え、えぇ…」
話しながらも近づく距離に灯子ちゃんがたじろぐ。私は玄関に降りて、彼女に近づきながらも腕を前に出し、彼女が手をかけていたその扉を押し込むようにして塞ぐ。
僅かに開きかけていた扉が、カチッと小さく音を立てて完全に閉まった。
「あ、あの…?」
「…………」
何をしているのか、何をしようとしているのかの自覚がない。
独占欲?嫉妬心?そんな子供じみたもの、あまり認めたくない。
体と、顔の距離が近づいていく。そろそろ息遣いが感じられるほどだ。
ぎゅっと、彼女が目を瞑る。
私は、短い距離を保ったまま、ぎゅっと彼女に抱きついた。
「わっ」
「……また、会えるといいな」
「もちろん、です。えと、……那々子さん」
「ぶっ」
思わず抱きついていた自分の体がぶれた。
「ナナコさん?!」
「あ、まずいですか?それじゃ那々子お姉さん」
「私、そんな改まって呼ばれるような人間じゃないよぉ?」
「でもお姉さんも、あ、いや那々子さんも私のこと灯子ちゃんって呼ぶじゃないですか」
「それは…」
「那々子さんって、とても呼びやすいです」
「あぁそう…」
………。
そうしてまた顔が近づく。
触れ合った唇は躊躇いがちに離され、視線が間近に絡み合う。
同時に頬が赤くなり、同時に目線を離した。
翌朝、
電車の向こうとこちら。一瞬だけど、それでも絡む視線。僅かな笑み。
そして今日も私たちの日常が始まる――
UP 2008/4/25
あとがき
ボリュームを出すことに四苦八苦してた頃。
そのためオチがないという。
ちょうど彼は誰刻に向かうまでの、過渡期的な作品かもしれません。
視点切り替え忙しくてすみません。
一応色はゲーム版と同じにしてみました。
もうちょっと(後半は特に)めりはりつけないといけませんね。
長くなりましたがここまでお読み頂きありがとうございました。
無断転載・引用禁止
Copyright(C) nokizaka All Rights Reserved