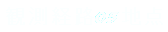ss
cross
・
・
・
・
いつも、通学途中の電車で乗り合わせる人がいる。
私はその一つ手前の駅からこの電車に乗ってくるわけだけど。
いつもと同じ時間の、同じ車両の、同じ扉から、その人はやってくるのだ。
きっと相手は私を気にも留めていないのだろうけれど、私はいつも気になっている。
年は20代半ばぐらい?
よくある黒の、なんの変哲もないリクルートスーツを身に着けてこの車両に走って乗り込んでくる。
気になる理由なんていつも見かけるからってぐらいのものだけど、それだけあればきっと充分。
ただの暇つぶしなのかもしれなかったけど、見かける度に私は勝手に親近感を持っていた。
たとえ相手が私に何の気も留めていなくても。
ただ興味深くて、いつも見つめていた。
それだけで充分だった。
・
・
・
(ふぅ……)
いくら経っても、この満員電車には慣れない。
ついでに言うなら、いくら経っても『東京』というものには慣れない。
人が多すぎる。海に囲まれている場所で生まれ育った私には、この広大な関東平野には馴染まない。
というか、なぜだか無性に泣きたくなる。
ここは、私の場所ではない。居場所なんてない。
そもそも大して希望に満ちて上京してきたわけではないけれど、思っていた以上に自分は都会への順応力がないのだなって思い知らされた。
まぁ、どこかで、慣れてしまったら終わりなのかななんて思っていたりもするのだけど。
習慣が違う、慣習が違う。
食べるものだってここでは慣れないお洒落なレストランばかり。
早く帰りたい…。
私はなんのためにここにいるの?
・
・
「ハァ……」
私は、何がしたいんだろう。
電車に揺れながらいつも思う。
流れ作業のように、起きてからここまで、食事をして制服に着替えて駅までやってきたわけだけど、機械的でもうあまり覚えていない。
目の前に写るのはどの人もまるで同じに見えるような、決まりきった服をした人達。
OLさんに、サラリーマンに、同じような制服の生徒に…。
私にはその姿がまるでもやにかかるように見えて、個性は感じられなかった。
(もしかしたら、私も、その切り取られた景色の中の一部なのかもしれないけど)
朝の満員電車内、こんなことを思うのは私だけだろうか。
みんな、きっと心の中はこれから一日のことで占められているのだろうか。
私は、まるでここに存在しないかのように、ただ、ぼんやりと考えをめぐらすだけ。
答えも出ないものを。
学校に行くのもいいけど、
家は誰もいない。
お母さんはいつも私より早めに家を出る。私の分の朝食を用意して。だから、家に戻っても仕方がない。
だからこうして、『なんとなく』ここまでの道を踏み出しているのかもしれない。
学校は退屈。
だからと言って特別行く場所もない。
毎日ふわふわ浮いたような生活の中で、私の生きてる実感はどこかへ飛んでいってしまいそうだった。
…そんな、足元がしっかりしてない私だから、どこかどこに行っても馴染めないのかもしれない。
(またあの街に行ってみようかな)
別にあの場所に特別することもないのだけど、それはどこも一緒。
することがないからこそ、そんな場所に行くのだ。
…………私は、存在しているよね…?
ここにいるよね?
もしかして、私だけが周りを見えてるだけなの?
「………」
ぼーっとしてる反面、内心は少し冷たいものが流れていくような気がした。
背筋が冷たい。
けど、その時突然後ろから衝撃があった。
「わっ!」
「あ、すいません!」
後ろからやってきたらしいサラリーマンは、そう口にしながら忙しそうに私の視界から向こうへと遠ざかっていく。
「痛い…」
でもどうやら私はここにいるみたい。
はたから見たらばからしいのかもしれないけど、私は自分の足元を見た。
…ちゃんと地に足は着いている。
手も、ちゃんとある。
自分の事を自分で見れないっていうのは、不便なものね…。
ん…?
(あの人は…)
・
朝は弱い。低血圧なのかしらないけれど頭がぐらぐらする。
いくら早く起きても、体たらくな自分はあと五分だのあと一分だのと誰かに言い訳して、結局ぎりぎりで家を出ることが大概。
起こしてくれるお母さんもいないから…って、私もそろそろ良い年した女性なわけだけど。
食事はトーストだけを口に放り込みながら、そのまま服を着替え髪を整えメイクをする始末。
今の姿を見られたら、きっと学生気分が抜けてないって、叱られるかも。
…叱られることが、幸せなことだって、こうして離れてみて初めてしったことだけれど――
……
…
「cross」
え…?
ちょっ、と…
何か違う…
おかしいな…
…………あ…
足元がふらつく…
もつれる―
(気持ち悪い)
「う……」
今更気づくなんて私…
―――まいった、なぁ…
すごい気持ち悪い。
こう、みぞおちの辺りからぞわーっと上にかけて這い登ってくるような。
考えてみれば、朝から胸の辺りがムカムカしていたような…。
(気持ち悪いぃ……)
そろそろ本格的にやばくなってきた。
揺れる電車内は気のせいかさっきよりも温度が高くなってきている気がする。
それでいてこのスーツ。通気性なんてあったもんじゃない。
「………………」
でも何で私、今の今まで気がつかなかったんだろう…。
知らずのうちに、疲れを溜めていたのかな。
ごまかしごまかし来たのかも知れない。上京してからこっち、それにももう慣れていたから。
それにしても、
このぐらいになって今始めて気づくなんて、本当にバカだ、私…。
(うぅ……)
苦しい…
頭までぐらぐらしてきた。
目の前のサラリーマンの肩にもたれかかるわけにはいかない。
体が…
…
私は、体が丈夫なわけじゃない。
徹夜なんてもっての他で、無茶なんてできない。
だから、
こうして、毎日こなすように同じ日々を送ってるのに…―――
……………泣きそう…
「次は○○~。次は○○ですー。向かって右側の扉が開きますー」
吐き気が襲う。けどそれがちょうどネガティブになりかけた私の思考を邪魔してくれた。
同時に停車席のアナウンスが耳に飛び込んでくる。
次で降りよう…
「ぷはぁ…!!」
ものすごい勢いで電車に乗り込んでくるラッシュをかき分けて、ようやくなんとかホームに降り立つことができた。
この駅は都心まであと僅かの駅だから、乗り込む人はいても降りる人なんて私ぐらいだ。
それでいてラッシュはピークに達する。
人ごみにもまれている中で、ふと頭に昨日の自分の姿が過ぎっていた。
思い返して見ればちゃんと思い当たるふしはあった。
昨夜私は、お酒を飲んでいたのだ。きっとあれのせいだ。
昨日帰りがけに間違えて買ってしまった果実酒を、家に帰ってきづいてからも何を思ったか煽ってしまった。正真正銘の下戸なのに。
今思うと、多少やけになっていたと思う。
ただの一つ言い訳させてもらえるのなら、あれは泡盛だった。
………。
それに輪をかけて寝不足という。本当に救いようがない。
半分涙目、そして口元に手を添えつつ這い出る私は随分ひどい様相だっただろうなぁ。
(人の目なんて、気にしてる余裕ないけれど、ね…)
………
「ハァ……」
あの後私は、何とか誰もいないホームのベンチまでやってくると、その後はただぐったりと伸びていた。
水も飲まず、前のめりにぐったりして、たまに襲ってくる吐き気に耐えている。
こんな最悪の体調には、こうしてただ風にあたり眼下の町並みを見ているのが丁度いい。
いつもの時間に向かう事は出来なかったけど、
それももうしょうがないよね…
――でも…
結構こうして、たまには歩を止めることも、いいのかもしれないな…
今まで見えていなかった景色が見えてくるような…
予定は狂わされてしまったけど。
――――
「………………あ、いたいた」
ついさっきまで同じ電車の同じ車両内のすぐ側に居たくせに。
いつもこの駅では開くホーム側の扉とは反対の扉にもたれかかっているものだから、
乗り込んでくる会社員やらOLさん達のラッシュでうまく降りることができなかった。
ようやくホームについて息をつき、辺りを見渡した頃にはあの人を見失ってるし。
ただ、具合が悪そうだったからそんなに遠くには行ってないだろう、って人が少なくなるのを
しばらく待ってそこできょろきょろして見たら、見つけた。
……私だって、勝手に親近感持ってる身とは言っても乗車中ずっとあの人のことを見てるわけじゃない。
扉の前で壁にもたれかかって、音楽を聴くなり目を瞑っているなりしていることが多い。
だから、いつ頃からあの人の顔色が悪くなりだしたかはわからないけれど、私が見たのはちょうど雲に隠れていた太陽が顔を出し、
車内に陽光が降り注いで何となく蒸れだした時。
『気持ち悪い』ってまさに顔に書いてある様子で、電車を這い出て行った。
で、何の未練もなく私はこうして今、電車を飛び出したわけだけど。
(なんて声をかけよう?)
一応、私の格好は典型的なセーラー服そのものなわけだし。
まぁ黙っていれば清楚に見えるだろう。けど、私にはあまりセーラーが似合ってるとは思わない。なんか…無理して着てるような。
(ブレザーの方が良かった)
今はそんなこと関係ないのだけど。
「…ふふ」
目の前前方には、ホームのベンチに腰掛け、気だるそうに前のめりで頬杖をつくあの人がいて思わず笑ってしまう。
具合が悪いところも、こんなだるそうな雰囲気も、初めて見るものだから。
(あぁ、怪しいかもね私)
まぁこの際、女だから、そして十代だからってことで、許して欲しいな――
――――
「お姉さん?」
「え?」
今のは…、…私の事?
確かめるまでもなく、眼下を見ていた私の視界の左端に、人の足がある。
一瞬だけれど、黒の革靴。白い膝下のソックス。細い足。
これだけで、学生だということは瞬時にわかったけれど、なんで?
そんな疑問が、私を振り向かせる。
「…………」
するとそこには女の子がいた。女子高生。
年は、高2,3年生ぐらい?
大人っぽい子。
「大丈夫ですか?」
「え、えぇ…」
どちらかっていうと『大人よりも大人っぽい』今時の子っていうか…、そんな感じなのに、こんなしっかりした話し方に、
少し戸惑ってしまう。
なんていうか、こう……見た目だけではもう少し恐そうというか…。
「今さっきの電車まで、一緒だったんです」
「え…」
「すごく青ざめた顔してたからつい気になって。一緒に降りてしまったんですけど」
「あぁ…………ごめんなさい、わざわざ…」
謝りつつも嬉しくて。
具合が悪いせいか人の何気ない好意が身に染みる。
…近頃では、こんなことを言われるのも久しぶりだし。
一人も慣れていたはずだったけど、やっぱり……
けど、それは置いといて…
「あの…あなた学校は…?」
「あぁ、…いいんです」
少し置いてから曖昧に笑う少女に、改めて私は彼女の姿を見た。
むむむ…
黒くて長い髪は、ストレートに下ろされている。
見れば制服はこれでもかってくらいの典型的なセーラー服。
…あぁ、私は学生時代垢抜けないジャンパースカートだったから羨ましいなぁ…。
こんな可愛い制服、…着てみたかったよ。…着てみたい。
けど…。
もう一度、目の前の彼女を視線だけを上げて見てみる。
…怪しい…?
東京だものね。何があるかわからないもの。気をつけなくちゃ。
たとえ一見、
良さそうな人でも。
綺麗で、スタイル良くて、垢抜けている子だけど、だから余計に。
それが私の、上京する前からずっとの決め事。
柔和な表情と雰囲気で、優しそうな子…。
でも気を許してはいけない、と思うの。
あぁ、でも、せっかく何の見返りも求めず、こうして好意で心配してくれたのに、そんなことを思うなんて失礼だわ。
いけないいけない…。反省しなきゃ…
私ったらなんてことを…
「――お姉さん、お姉さん」
「へ」
「何だか考え事してたみたいだから」
「あ、あぁ……ごめんなさい…」
なんだかばつが悪くてつい謝ってしまう。
それにしても…
なんでそんなに優しいまなざしで見つめてくるの??
意味もわからず、
目線のやり場に困って、自分の足元を見るしかない。
「さっき急に暑くなってきましたもんね」
「そ、そうなの…?」
「そうですよ。朝から曇ってたのに、一気に太陽の光が降り注いで」
「そうだったんだ…」
どうりで、急に気持ち悪さが襲ってきたわけだ…それすら気がつかなかった。
っていうか、いつのまにか気持ち悪さが抜けていってるよ。
そろそろ…
「どこに行くんですか?」
「いや、お水をそろそろ買おうかと…」
「買ってきますよ。まだ本調子じゃないでしょうし」
「でででで、でも…」
「行ってきます!ちょっと待っててください!」
「い?え?いや、あのちょっと…っ!」
お財布から小銭を取り出してたらあっという間にセーラー服の子はいなくなってしまった。ぼんやりと見つめる先には、自販機に向かって歩いていく彼女。
私は…小銭を持って呆気に取られる他ない。
「お、お金……持って行ってよ…」
おごってもらうなんて、申し訳が立たないよ………!!
・
・
「あ、ありがとう!……ごめんね、わざわざ」
「いえいえ」
「あの、これ、お金…」
「あぁ、はい」
素直に受け取ってくれた。あり難い。
受け取ったペットボトルのミネラルウォーターは僅かに汗をかいていた。
冷えたそれを蓋を取って、僅かに含んで口の中を潤してみる。
……うん、大丈夫みたい。
ところで…
「あ、あの…」
「はい?」
「わ、私もう大丈夫だから。あなたは、その…」
「学校、今日休みです」
「………………うそでしょ」
「…………どうでしょう」
止まる会話。うまくやり込められてる私。年上なのに…。
「それじゃ、単刀直入に言います」
「へ?あ、はい……どうぞ」
な、なんだろう……
「私と、遊びませんか?」
「は?」
「お姉さんまだ具合悪そうですし。ほっとけないです」
「い、いやあのその、今遊ぶって……」
「ついでというか、今日一日、私と付き合ってくれませんか?」
「えぇ??」
「あ、付き合うって、遊ぶってことです」
「いやそれはわかるけれど…」
他にどんな意味が?
「どうですか?」
「いや、でもその……あなた制服じゃない」
「あ、そうですね」
「まずいと、思うの」
「お姉さんの予定は?」
「私は、……もう今日は潰れてるし」
「じゃぁ、制服だけですね?問題は」
「あ、そうじゃなくてその……」
「大丈夫です!薄いコート買いますから」
「えぇ?!」
なんて行動力のある子だ…。東京の子はみんなこうなのかしら。
「具合はどうですか?」
「いやその……大分良く…」
「じゃぁ、行きましょう!」
「えぇ??!」
こうして私は、唐突に出会ったセーラー服の少女に、名前を互いに名乗らず知らないまま、朝の殺伐とした駅のホームから引きづられるように連れられていってしまったのである。
「…………」
「ん?どうかしましたか?」
「い、いや何も…」
今さっきまで私はホームの椅子に腰掛けてたわけだけど、こうして並んで歩いて見ると、……どうにもそんなに背が変わらないせいかどことなく複雑な思いにかられる。
私も、女としては背は低くないと思う。
けど彼女もまた、今時の女子高生にしては背はある方だと思う。
問題は、私と対して変わらないため何だか二人の年齢はそれほど変わらないように見えるような、
……とどのつまり服装のおかげで何とかどちらが年上かわかるけれど、彼女に比べると何だか私の方が子供っぽいというか……。
「それじゃ、最初はコート買っちゃいましょう」
「えぇ?!本気……?」
「もちろん」
「……」
行きずりで出会った相手と、本気で遊ぶ気?
それは、口には出さなかった。
「ものすっごく安いの、買いましょう」
「ちょっと待って、お金は、私に出させて」
「え、ダメですよ。そんなの」
「こっちはもっとダメ!私が言ったのに、……つまり、私が買わせたってことになっちゃう」
「だって、私が言い出したんですよ?」
「それでも、よ」
「………わかりました」
「…………」
さっきみたいに、また優しく笑ってくれる。
うーん……
何だか、……どうにも困ってしまう。
「こっちにありますよ。ちょうどいいお店」
「あ、ちょ、ちょっと待って!」
さっさと行ってしまう彼女に、私は慌ててついていく。
「この辺り、詳しいの?」
「まぁ、多少は」
「ここ?」
「えぇ。この辺りって、結構駅前の商店街は若い人多くて活気があるからこういうお店も多いんですよ」
目の前に現れたのは典型的な若者向けの服屋である。しかし…ユニセックスではあるだろうけど少し男の子っぽい。中には女性物もあるみたいだけど…。
そのままスタスタ中に入っていく彼女に慌てて後ろから声をかける。
「どうして知ってるの?ここはまだ、都心には入ってないぐらいの場所なのに」
「…………まぁ、色々と…」
「…………」
まぁ、いいか。
辺りは僅かに薄暗く、そして雑然と薄い布のコートや若者向けのトレーナーがディスプレイされてある。迷う素振りも見せず、彼女はさっとハンガーにかけられてあったベージュのコートを手に取った。
「これでいいです。女性用みたいだし。薄いし安いし」
「…………1500円…」
こんな安い服があるんだ。
「ありますよ。まぁデザインも悪くないし。制服を隠すには手ごろかな」
「では、これ買ってきます」
「えぇ、ちょ」
「――――これください」
ちょっとちょっと。既にもうレジに向かっちゃってるし。
あっという間に購入しタグを取ってもらって羽織れば、そこにはすっかり制服の隠れたさっきまでのセーラー服の子。
「どうです?何だか冴えない探偵みたいですけど」
「まぁ、悪くないと思うよ」
スカートを若干残す程度の丈のコートは、さすがに靴下とその革靴までは隠せないからやっぱり制服っていうのはわかってしまうけど、
それでもセーラー服が目に飛び込んでくるよりはよっぽど刺激は少ない、と思う。
ただまぁ、僅かに前を開けてるから、ちらちら目にはつくんだけど。
「それでは行きましょ」
「えぇっ」
「まだまだ始まってもいないですよ」
日が出てきて暑くなってきたせいか彼女はコートの腕をまくる。
そしてそれが出来ない暑苦しいスーツの私の腕を取って駅へと向かおうとする。
ひぃ、助けてぇ………!!
***
「―――で、どこに行くの」
「さぁ、でもこの線なら、都心には嫌でも出ますよ」
「まぁね…」
あれからいくつかの線が乗り入れてる都心近くの駅で乗り換えて今はこうして午前中の人の少ない車内で、彼女はドアに背をもたれ、
私はつり革に掴まっていた。はぁ。
「…………そんなに嫌ですかぁ?」
「いや、嫌ってわけじゃないけれど、」
「それじゃ何です?」
「んー………よくわからない」
「そうですか」
からっと笑う彼女に、ほっとする。気にしないでいてくれるみたい。
実際嫌じゃないけど…………そう、戸惑ってる私がいる。
ずっとこっちに着てから真面目そのものの生活を送っていたから、こういうのって、何だか慣れない。
っていうかその、何をしてても、ここでは何だか馴染まなくて、ズレを感じる気はするけど。
「お姉さん具合はどうですか?」
「あぁ、うん。もう大丈夫みたい」
「…………でもゆっくりできる所がいいですよね。任せてください。お昼は静かにとれるところでとりましょう!」
「えぇ」
はりきってる彼女に、またついていけず戸惑うけど、でも言うとおりにお任せすることにした。
「って」
「はい?」
「何でこんなところ知ってるのー?!」
「友達に連れられてきたんですよ。一度」
「はぁ……」
思わずため息が出る。今時の子はこんなところも知ってるのか…。
途中地下鉄に乗り換えてこのケヤキ通りで有名な繁華街へとやってきた私たち。
今は何だか入りづらそうな、やたらにお洒落なレストランが目の前にある。
「席あるかな…」
今はまだお昼ちょっと前。
「あ、あるみたいですよ」
「はぁ」
「早く早く!」
慌てて連れ込まれたそこは中が半個室になっていた。
アンティークな雰囲気も備わっているそこは、皆静かにゆっくりと過ごしている。
「どうです?いいでしょ」
「そうね…」
「ここならゆっくり出来ますよ」
…
……
食事中、
「トマト、嫌いなんですか?」
「え?あぁ、うん。ちょっとね…」
「ふーん…」
生返事を返しながら彼女はさっきまで動かしていた両手をフォークとナイフを持ったままその動きを止める。
何か考えていたようだけど、気づくとその右手がふいっと動いていた。
「あ」
「もらっちゃっても、いいですか?」
「う、うん」
いや、もう食べてるよね?
でも、何だかおかしいな私。
あっという間にフォークに刺したミニトマトを食べたと思ったら、さっそく自分の食事に戻る彼女を見て思う。
だって、食べ物の好き嫌いを聞かれただけで、どうしてこんなに胸がドキドキするんだろう。
随分調子も良くなった――
あれから二人で彼女の連れてきてくれたレストランで昼食を取ったわけだけど、
お昼時なのに随分落ち着ける場所で、ゆっくりと時間を過ごすことができた。体調も、比較的胃に易しい物を口にしていたら随分と調子が戻ってきていた。
彼女はメニュー選びにも食事中の会話にも、とても気をつかってくれた。
今はお店を出て、二人で街中に佇んでいる。
「――どうにも馴染みませんか?」
「え?」
「…こういう関係」
「あ…」
少しぼーっとしていて、彼女の言葉も”なんとなく”聞き返していた。もちろん瞬時にどういう意味なのかわからなかったのもあるのだけど。
だけど、気づいて顔を上げた時、さっきまで曇りなくはつらつとしていた彼女がほんの少し、不安そうな寂しそうな顔をしていたから、
今になって私は気づく。
そうだよ、彼女だって…
私となんら変わりない、普通の女子高生なんだ。
むしろ私なんかより年下で、きっとこういう行動だって勇気が必要だったんじゃないかって。
さっきまで東京人だとか今時の子だとか、そんな先入観とか表層ばかりで見ていたけど、今になって初めて彼女を見た気がする。そして今更ながら慌てた。
「念のため言っておきますけど、こんなこと、しょっちゅうしてるわけじゃありませんからね。……初めてですから」
誤解のないようって、念を押す彼女に慌てて私も「もちろん」とうなづく。彼女は別段怒ってる風ではなかった。
やっぱり優しく笑っている。しかしさっきまでよりもぐっと親近感みたいなものはより感じていた。
「ごめんね、私ったら…」
そもそも具合の悪くなった私を気遣ってしてくれたことなのに。
相手が男性ならともかく彼女は私よりも年下の学生なわけで。
警戒するなら彼女であって私だなんてまるでお門違いだ。
しかし、元来人見知りをする自分の性格はやはり事情を改めて認識しても思うように言う事を聞いてくれない。
「そうだ。今日限りの関係って、そう思えばいいんですよ」
「え?」
「………まぁ、実際そうなんですけど……、……とりあえずそれは置いといて、どうです。『明日に引きずらない』これを二人の間に約束するっていうのは」
「引きずらない?」
「そうです。明日には、…………そう、まるで出会ってなかったみたいに、元に戻るんです。昨日までの、…日常に。」
「…………」
「そう割り切っちゃえば、色々と思い切れるかも」
「…………そうかもね」
大胆な発想だなぁ。そう思ったときには小さく笑ってしまっていた。
それをすかさず見止めた彼女が本当に嬉しそうに笑った。
『今日だけの関係、か』
不思議だね、そう思ったら急に、
なんだか思いがけないほど大胆になれる、そんな気がしたんだよ――
今は、お昼を取ったレストラン前のケヤキ通りを散策しているところだった。
お昼も過ぎ、随分とのんびりとした穏やかな空気が街にも流れていると思う。
「あ、ちょっと待っててね…」
「はい?」
私は、今更ながら。ほんっとうに今更ながら携帯を取り出し、……会社に電話した。
欠勤報告をすると、案の定、いやそれ以上にものっすごく怒られた。ただひたすら電話に向かってぺこぺこ頭をさげ謝る私。
ただ、それも最初だけでそもそも出勤途中に体調が悪くなった事と、今はもう大丈夫な事で多めに見てもらえたようだ。
……次はないようだけど。連絡は早めにするようにと、注意を受ける。しかし日頃の勤務態度を認めてくれたのかそれ以上は
不必要にお小言は言われなかった。
ちなみに前日の飲酒については説明していない。もちろん体調不良の原因が二日酔いだということも。
「ふぅ……」
「……大変、そうですね…」
恐る恐る声を掛けてきた彼女に振り返って苦笑いを返す。
「まぁ、仕方ないよ。これでも、社会人だから」
言ってて自分で違和感を感じる私だった。
「それ、可愛いですね」
「……あ、これ?」
気を利かせてくれたのか、話題を振られた先、
指差された先を追ってみると、そこは私の左手首。
厳密にはそこにかかっているブレスレット。
「なんだか変わってますね。可愛い」
「そうかな。ありがとう…。………これはね、」
ガラス玉が一つアクセントになっているそこに、紐を編んだとてもシンプルなブレスレット。
けど、そのガラス玉にしても、紐の色にしても赤や青などの目に鮮やかな装飾で確かにどこか目を引く。
「これは、母が作ってくれたもの」
「お母さんが?」
「そう。手作りなの。………こっちに来る前にね」
お守りって、そう言って作ってくれたもの。
「これを見るとね。実家と故郷を思い出すっていうか。あ、私生まれが沖縄なのね」
「そうなんですか!」
「…そんな感じする?」
「うーん、……言われてみればっていう気もしますけど、でも言われないとわからないかも…?」
「そっか」
とても揺らいだ位置にいるのかな、私は。
そう思っておかしくてほんの少し笑ってしまった。
「お母さんか……」
「…?どうかしたの?」
「あ、いえ…。……うちってお母さん仕事忙しいから、近頃じゃあんまりそういう交流ないなって」
「…………」
「いいですね、そういうの。今度私も、お母さんに作ろうかな…」
「…………、でも、日頃ぜんぜん会えないから」
「あ、そうですよね…」
「電話ばかり。毎日寝る前にね。それとか夕食時に食べながらとか。…………東京は、どうにも馴染めなくて」
……不思議。
こんなに私が自分のことを語るだなんて。
地元の友達にだってこんなに、自分から話したりなんかしない。それだけ、この刹那的な時間は、普段では躊躇うことを思い切らせる不思議な、何かがある。
***
「東京にはどうにも馴染めなくて」
そう始まった彼女の呟きは、私の中にずっとあった引っ掛かりと符合した気がした。
だから、そう……、いつも憂いだ表情というか、気になってしまうような何かがあったのかな、って。
「まず海もないでしょう。それに、寒暖のさも激しいし」
「そうですねぇ」
「お洒落な街ばかりだし、と思ったら何だか寂しいお店も多いし。無機質なビルもたくさん。空気も全然違うの。流れてる空気が、
…ううん。そうじゃない。町並みが、違うの。虫とか動物だって、植物も、建物も、全然違うから……」
「…………」
横目でじっと見ていた表情は、言葉と共に徐々に曇っていく。目が伏せられ、悲しげに俯き加減になっていた。
「あの…」
「…………」
やりきれない。そんな表情。
やっぱり私、この人のこと…
私は、黙ってしまった彼女に、手を見つけるとぎゅっと両手で握りしめた。
「え?」
「私も、一緒ですよ」
とまりかけていたその人を、その人の気持ちを引っ張るように、繋いだまま私は歩き出す。
「一緒?」
「そう。一緒です。私も、いまいち馴染めませんから。学校に」
「そう、なの?」
「えぇ。まぁ、これは私の問題でしょうね」
どうにもこうにも、私は学校内でみんなと一様に同じ毛並みで、雛形のように生活できない。
個性を押し殺して型にはまれない。
浮いた私を受け止めてくれる環境も、なかった。
学校とは、従来そういうものなんだろうけど、そういうものだって、納得できないのが私だった。
「特別何かがあるってわけじゃないんですけど。別に普通に生活しようと思えばできるんですけど。
なんていうか、生活してて常に違和感が付きまとうというか。どうにも馴染めてないんですよねぇ、私」
「……」
「結構こういう目に見えない何かの方が、しんどかったりしますよねぇ」
簡単に言えば、合ってないんだ、私。
「…………」
「あ、の……」
そこでどうしてか私、押し黙ってしまった。
何だか、次の言葉が出てこない。
お姉さんに居心地悪い思いさせてるかもしれないって、そう心の片隅では思いもしたけど、でもとまらなかった。
何か具体的なことを考えていたわけじゃない。何を考えているのか、自分でさえもよくわからなかった。
ただ、なんとなく黙ってしまった。沈黙がきっと、私に降りかかってきたんだと思う。
「…………」
「あの!」
「あ、はい」
「えっと、その…、先行こう?」
「そう、ですね…」
返事をしておきながら、まだ私は上の空だ。
促すようにまだつながれたままだった手を引いて前に乗り出すお姉さん。私は今さっきとは逆に、彼女に引かれる形で後を追う。
「あ…」
ようやく先を見つめた私に、視線が合ってにこっと微笑んでくれるその人。
さっきまでとは全然違う、大人っぽい優しい笑みだった。思わずどきっとしてしまう。
私らしくないような――少し恥ずかしくなってしまって顔を俯かせる。そうしていたら何だかさっきまでの気持ちも頭を占めていたものも
さっぱりどこかへ消えて行ってしまっていた。高鳴る鼓動が、変わりにどこかへと追いやる。
(なーんかおかしいなぁ、私)
小さく胸を押さえた。
……
「…………」
「…………」
なんとなく、沈黙が押し迫る。
二人の間は、会話もなくただ静かになった時だけが流れていた。
……私は、あまり気まずいとか思う方ではないけれど、ちらっとお姉さんを盗み見てみると、何だか何か考えているような思案顔。
「あ、の…!」
「え?」
あまり気にする方ではないのだけれど、思わず口がついて出た。
「すみません、……いきなり黙っちゃって…」
「あぁ、ううん。大丈夫大丈夫。気にしてないから」
「そう、ですか」
さっきからこんなやり取りばかりしている気がする。
「それよりも」
「はい?」
「今日は、目一杯その…、遊んじゃおう?」
「…………」
気づくと未だに握られたままだった。私の手。言葉と共にさらに両手で正面からぎゅっと握られた。
ほんの少し自分の目が大きくなった気がして、ぱちぱちと改めるように目の前のお姉さんを見つめてしまう。
意識してしたわけじゃないんだけど、そうしていると目の前のお姉さんの顔が徐々に赤くなってきた。
「あ…、……はい…!」
ようやく我に返ったというか、お姉さんの言葉が私が最初に掛けた言葉と同じだって気づいたら、自分でも驚くぐらい
嬉しい気持ちになって笑顔を返していた。
……
…
「よぉ! ――!」
「ん?」
「え?」
当分続くだろう長いけや木通りを二人で当てもなく歩いている時、明らかにこちらに向かってかけられている声に二人がそれぞれの態度で反応する。
実際自分側にかけられたものなのか、確かめるために声のした方に振り向いて見ると、そこにはさも知り合いを見つけたといわんばかりの目をきらきらさせた男の子が居た。
「よぉ!どうしたんだよ、こんなところで」
「え?あぁうん」
その彼はこちらに駆け寄ってくるとそのまま真っ直ぐ彼女の正面に向き直る。
すぐに隣の私に気づくと、気を使うように軽く頭を下げてくれた。私も同じように下げ返す。
「…………」
彼女は彼を見据えながらもどこか困ったように私をちらっと見る。
しかし、
今、彼女の名前呼んだよね?
うー、せっかく呼んでいたはずなのに、突然の事でそれまで気が抜けていたのと、周囲の雑音で全く耳に入ってこなかった。
………
しかし、やたらかっこいい。
身長もあって髪も服装もかなり気を使ってるのがわかる。その上元の顔も端正なのだから。…見た目だけではちょっと軽そうだけど。
向こうで会話を続ける二人を私はつい後ろから興味深げにしげしげと眺めてしまう。
やっぱり話し振りを聞いていると彼女みたく意外に中身はしっかりしているみたい。
今時の子はみんなこうなのか、それとも彼女の友人はやはり似たタイプの子が引かれるのか。
…こうなってくると自分の方がよっぽど子供のように見える。
学生特有のものなのか、それとも元からなのか。
…きっと後者だろうけれど。
その考えで行くと、やっぱり私は元から子供っぽく学生時代も年相応であって今もまたこんなものだ。
「…………」
人知れず少し落ち込む。
しかし…、
(なんだ、友達いるんじゃない…)
男友達だけど、この際関係ない。
(私なんて上京してからこっち、職場仲間といえる人はいるけれどプライベートでも親しくするような人なんていないっていうのに)
東京には親戚は遠戚含めてもちろん出てきてる人もいないわけで週末に改めて出かけたり、よくしてくれるような知人もいない。
仕事後はもちろん業務以外の誘いでは何かと付き合いの悪い私には個人的に踏み込んだ付き合いのできる友人もできるわけなく……って、あれ、
…………こう考えてみると随分私寂しい生活してるなぁ…。
何だろう。この典型的な寂しい独身OLライフ。まだ20台半ばとは言えどうにも廃れたようなイメージ。
こ、これはちょっとななな何とかしないと……
「…………」
不意にふっと、顔を上げ会話を続けている二人を見る。
最初は男の子に、そして次は彼女に。
…………なんだろう。
今なんか、胸がずきっとしたような。
愛想笑いなのかもしれないけど、男の子と話す時に多少笑みを零す彼女の横顔。
なんか、おかしいな、私…。
なんでこんな胸がきりきりしてるんだろう。何だか、とがっていく様な。貧しくなっていく感じ…。
今時女子中学生でもないのに。
??ん?
顔が赤くなる。
(??なんでなんで??)
慌てて私は後ろに振り向いて頬を両手で隠した。やたら熱い…。
***
「綺麗な人だな」
「え?」
「あの人。知り合い?それとも親戚とか?」
「んー……どうでもいいでしょ」
「なんだよ。連れないな」
顔では和やかに笑いつつ時折微妙に睨んでしまう。
「ちょ、何だよ、怒るなよ」
「……別に」
「こんな時間にそんなコート着てそんなに年変わらない人と歩いてたら気になるだろ」
「ふん……」
様子からして、言葉に嘘はないみたいだけど…。って
「『そんなに年変わらない?』」
「ん?あぁ。服装が真逆だけど、そんなに変わらないもんだろ?」
「…………」
あんた、どんだけストライクゾーン広いのよ。
「ね、もう行っていい?」
「な、なんだよ!今日はほんっと連れないなぁ」
「だってさぁ…」
ごめん。他意はないんだけどさ。邪魔されて実は結構いらついてたりするんだよね。
「ご愁傷様。今日は運がなかったね」
「はぁ?」
………
「お姉さん?」
「え!?」
「どうしたんですか?」
「いや別に……」
どうやら私が自分の世界に浸っている間に声をかけてきた男の子との会話は終わったようだった。
不意に後ろから呼びかけられ、さっきまでと同じ至って普通の態度で接しられて余計に焦る。
私は慌てて頬から両手を離すとぎこちない態度で彼女の正面に向き直る。
「…………」
しかし、誤魔化している私に彼女はどうしてかすぐに納得してくれず、探るように正面からじっと見つめられる。
私は、真っ直ぐ向けられる視線に居心地の悪さを感じふいっと視線を逸らしてしまう。
「話はもういいの?」
「え?あぁ、別にいいんですよ。彼もこんな時間に知ってる人間に出会ったってだけで声をかけてきただけですから」
「そうなんだ…」
何だか少し呆気に取られてしまう。
だって彼女はさも普通といわんばかりの態度で私に話をしていたから。
相手が異性ならば多少意識や態度が変わったりするものだけど、彼女のそれはまさに、……そう
女の子と出会ったかのような、まるで何の意識も持たない相手といわんばかりの言いぶりだったから。
まるで空気のように、何の違和感なく男性と話したり話題に持ち出すのは、私には少し馴染まずそして僅かに関心に近い憧れを抱く。
すごいなぁ。
いや、実際彼女の見た目だけを取っていえば、こんな付き合い方をするような感じはするのだけど。
今時の子は。東京の子は。
ううん、きっとそうじゃないと思う。きっとこの子が、そういう子なんだな。
人に接する時のしっかりした態度と、それと相反するある意味では外見通りの細かいことは気にしない大柄な人となりに、多少戸惑いは隠せない。
こんな子と、私なんかで釣り合うのかしら?
なんかおかしくない?私なんかが一緒にいて。
釣り合ってないような。正直釣り合ってないよね。
「はぁ」
「どうかしたんですか?」
腕を組んでうなっていたけど、思わずため息が零れる。
そうしていると不意にすっと片手を握られた。
「彼、サボり常習犯なんですよ」
「え?あぁ、そうなんだ」
……はっきり言って会話なんて頭に入ってこない。
どうしてそこで手を握るの?
しかし本当にさりげない仕草で、ほとんど力も入ってない状態で手を取られたものでどうにも反応しがたい。
そっと触れられる感触はすごくきめが細かくて潤いみたいななめらかさもある。そのまま滑らかな動きで手を指先だけで軽く繋がれてしまう動作が、
嫌に私をドキドキさせ、顔から上がやたら熱く温度が上昇してきた気がする。
思わずそのままになってしまうが、さっきまでの暗雲が立ち込めていたような心情もすっかり太陽に退かされているように頭から過ぎ去ってしまう。
それ自体に自分が気づいていたのか気づいていなかったのか、よくわからない。
「私がなんでこんなコート着てるのか気になったみたいで」
「あぁ、確かに」
「いきなり、いつもは見慣れないコートに身を包んだ知り合いがいたら、反応しちゃいますよねぇ」
「うん、そうかもね、って………もしかして、サボり常習犯『仲間』なの?」
「え?……あはは、いやだなそんな。人をまるで同じ種類の人間みたいに括らないでくださいよー」
いや、だから同じ種類(タイプ)の人間なんじゃないの?
しかし、何だかこんな焦ったような感じの彼女を見るのは初めてで少し新鮮。
「彼はよくサボって街を徘徊してたりするんです。私もたまに、会ったりするだけで私は決してサボり常習犯だなんて、ねぇ?」
「…………」
「そ、それに彼は同じ学校の人間じゃないんですよー?中学まで一緒だったんですけど、今は別々の学校ですし、本当にたまたまなんですよー」
………同じ学校じゃないんだとすれば、なおさら余計に、ただのクラスメートってわけじゃなくてそれこそ『友人』ってやつよねぇ。
私には、あそこまで割り切って付き合える異性の『友人』はいないなぁ。
「学校変わっても相変わらず本当に偶然にたまに会ったりすることもあって」
「…………」
…なんだろう。さっきから彼の話ばかりする彼女に、ほんの少しいらつきが募る。
まぁ眉間にしわがほんの僅か寄るぐらいなんだけど。何この感情。
「本当に私と違ってしっかりしてないっていうかしょうがないっていうか――」
「ふーん」
「あ、あの、お姉さん?」
驚いた。随分と自分の口から低い声が出たもんだ。
っていうかさっきから何考えてるんだ、私は。全く嫌な人間になっている。さっきからそう、女子中学生でもあるまいに!
(しっかりしろ_!私)
思わず子供っぽい自分の行動に多少の自己嫌悪を覚え心の中で渇を入れる。
私だってもういい年した大人なんだからもう少し自覚を……って、あれ?
「…?」
違和感を感じて後ろに振り向く。
すると隣の彼女はしっかりと手を繋いだまま、だけど俯いて立ち止まってしまっていた。
私は同じ調子で歩いていたから、思わず後ろに引っ張られてしまう。
しかし彼女は手を僅かに前に引っ張られながらも下を向いている。あれ…?
……あのその……
「…ごめんなさい…。何か、その怒らせちゃいました…?」
「うっ…」
ってちょっと!
何かと思ったらいきなり上目使いで恐る恐るそんなことを聞いてくるなんて!
「な、なななななにが」
「いやその、……気づかないうちに不快にさせてたかなって。それか見損なったかな、とか。私ばっかりしゃべってるし…」
「い、いや全然。全く。本当にそんなことないから」
思わず顔の前で片手を振って全否定してしまう。
さっきまで大人っぽいと思っていたら、何その年相応かそれ以下の幼い涙目!
「本当、ですかぁ…?」
「本当に本当。全然、気にしてないから、ね…?」
「………良かったぁ」
そう言って見るからに彼女は胸を撫で下ろす。
さっきまで不安げだった表情が一気に安堵に変わる。私はそれを見ていてつい疑問を感じる。
別に、私たちは旧知の仲なわけじゃない。姉妹でもなければ友人でもなく、今朝会ったばかりの、
そう他人…だったような関係だ。しかもこんなに年の離れている。それなのに、……
それなのに、そんなに不安に思うものなの…?
わからない。
続き
UP 2008/4/25
あとがき
無断転載・引用禁止
Copyright(C) nokizaka All Rights Reserved